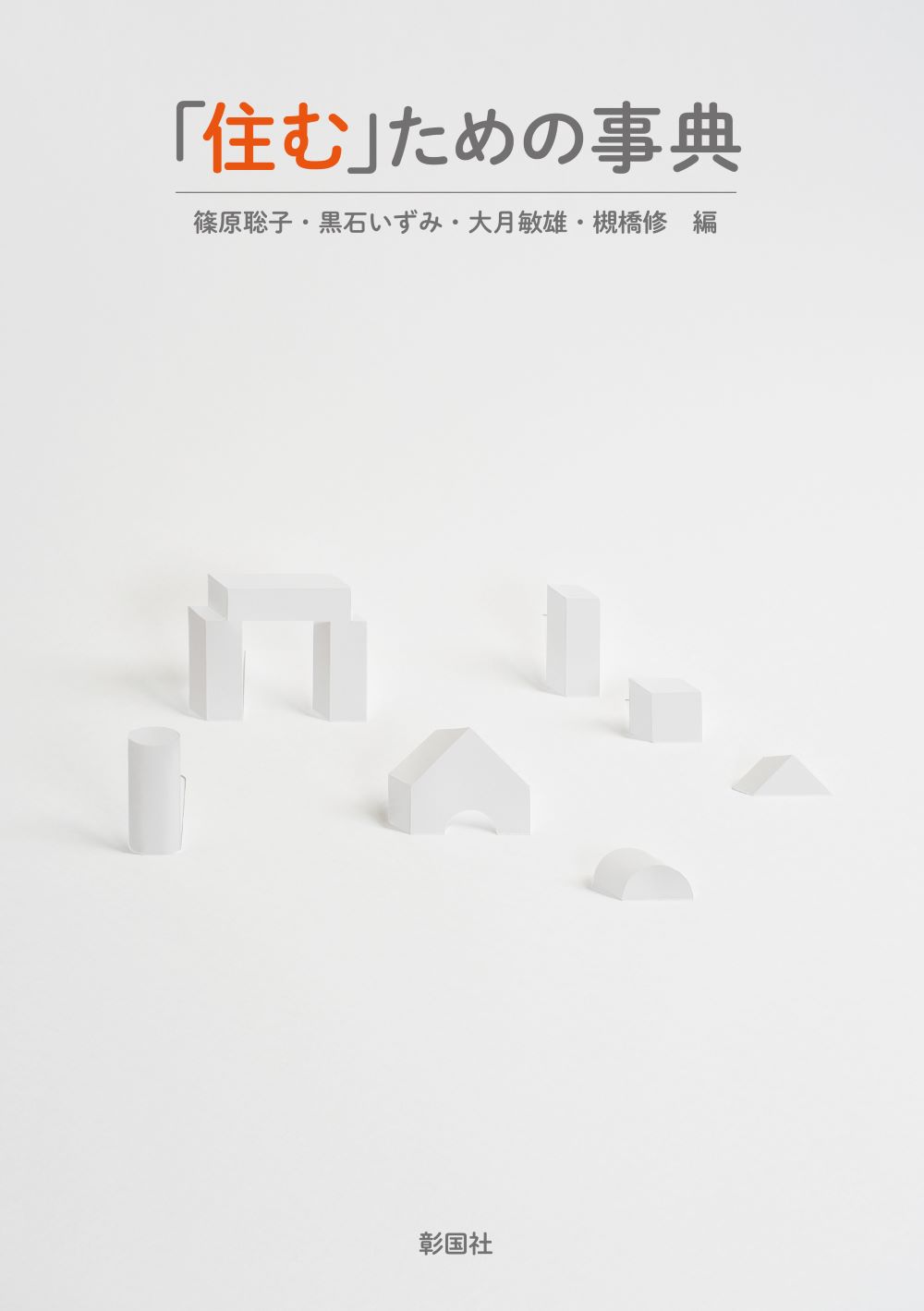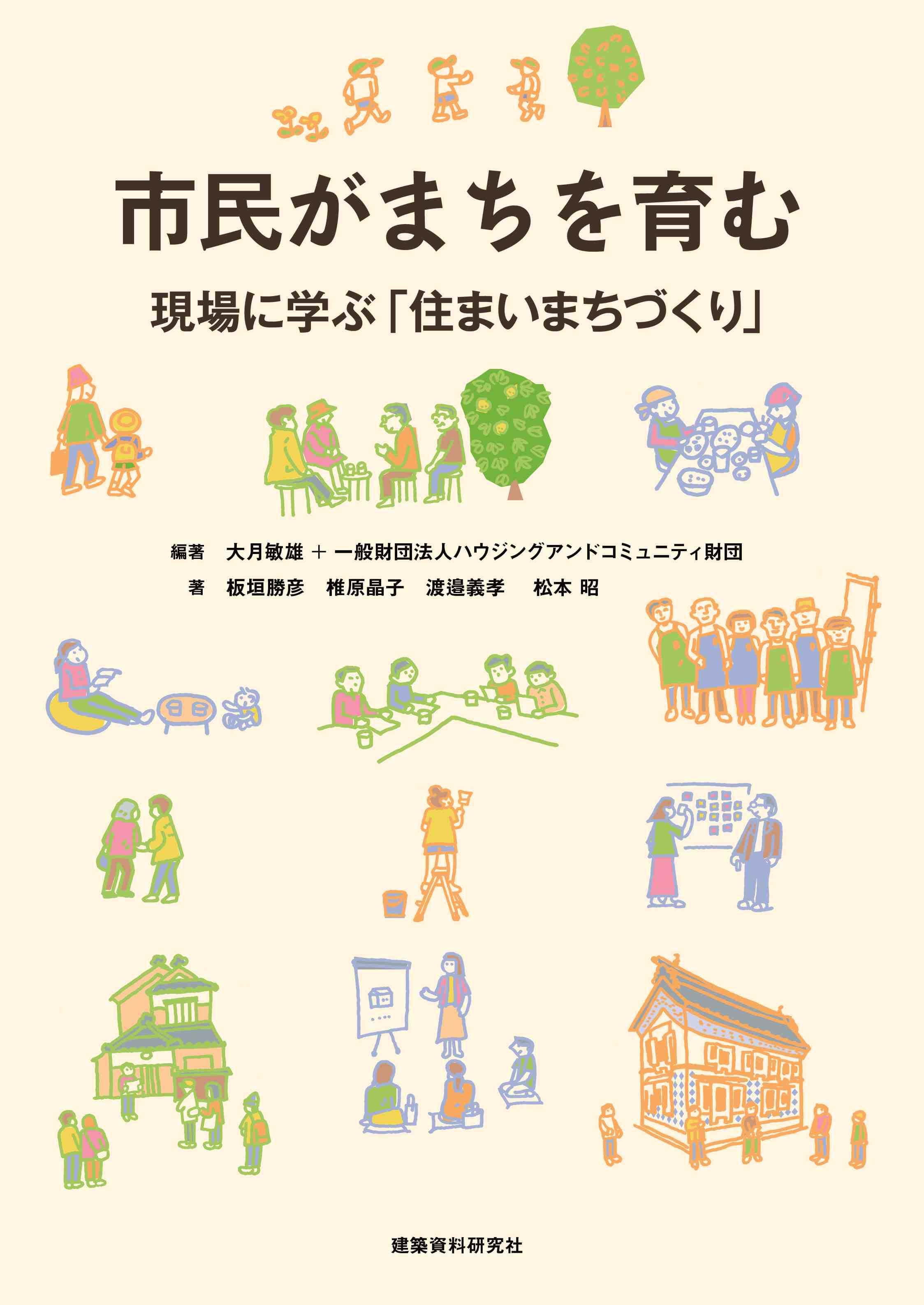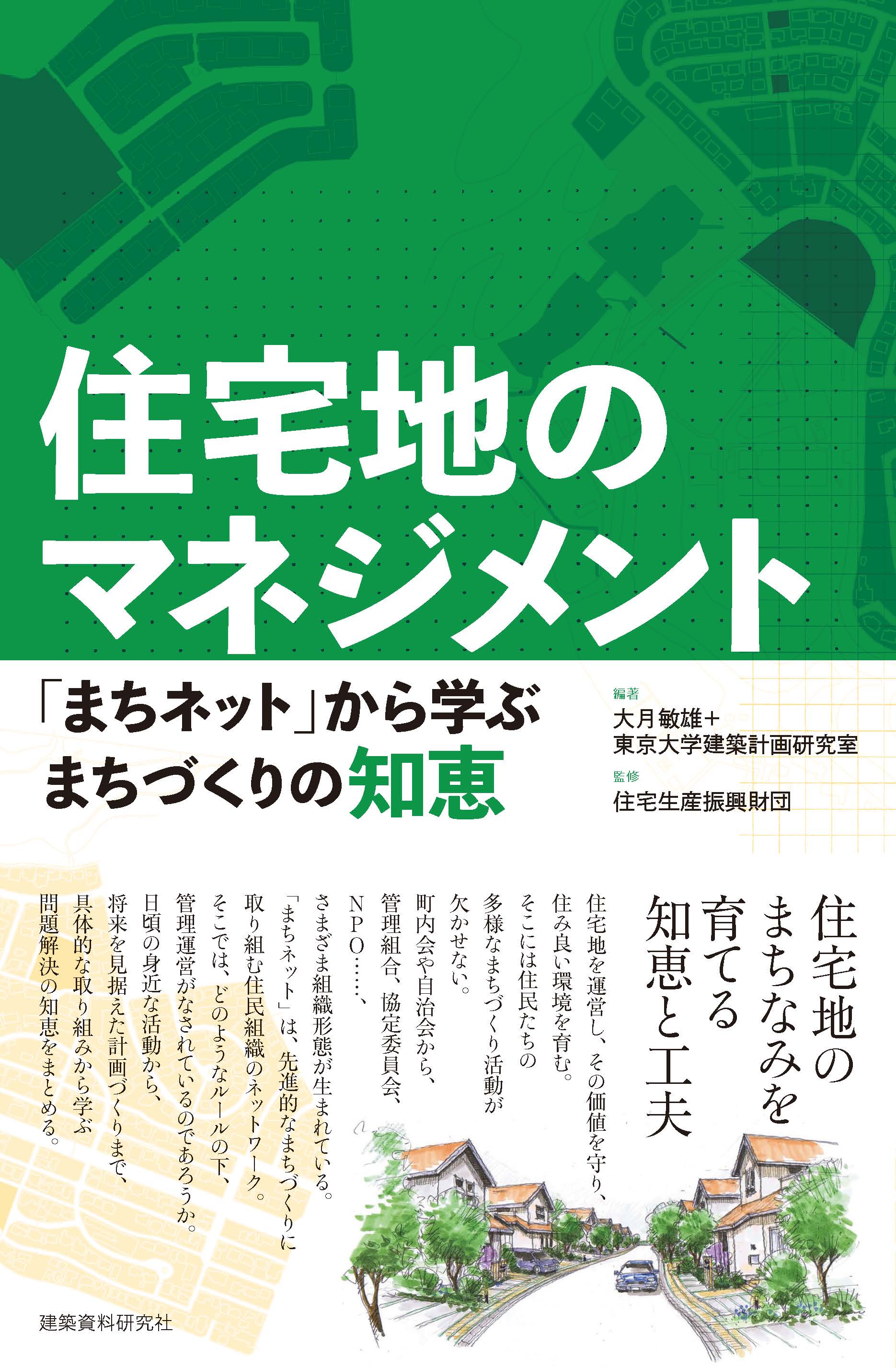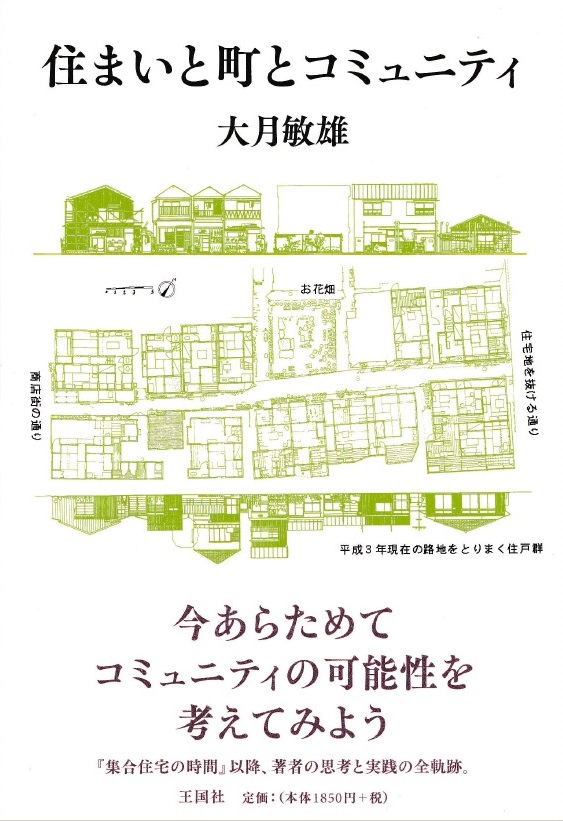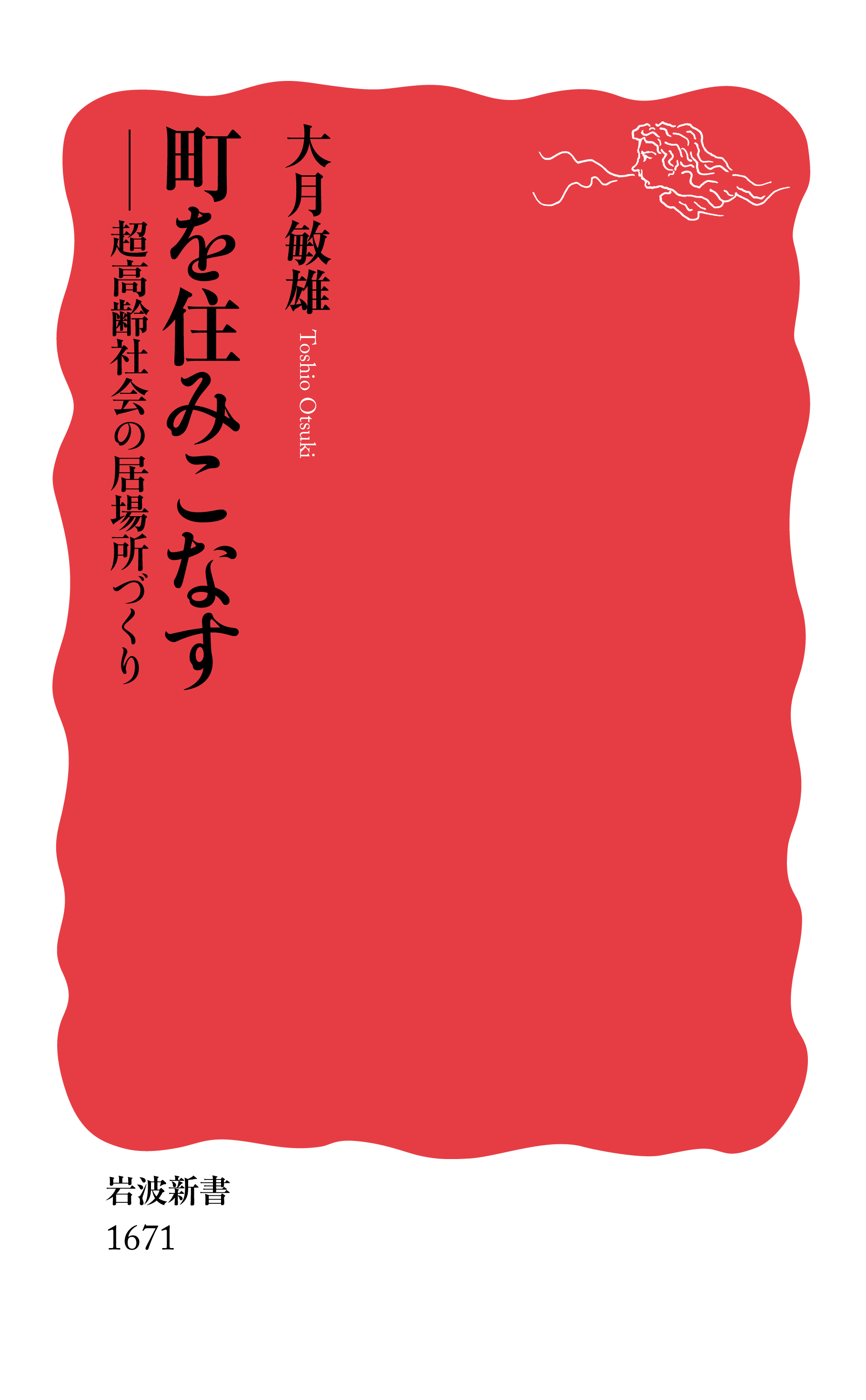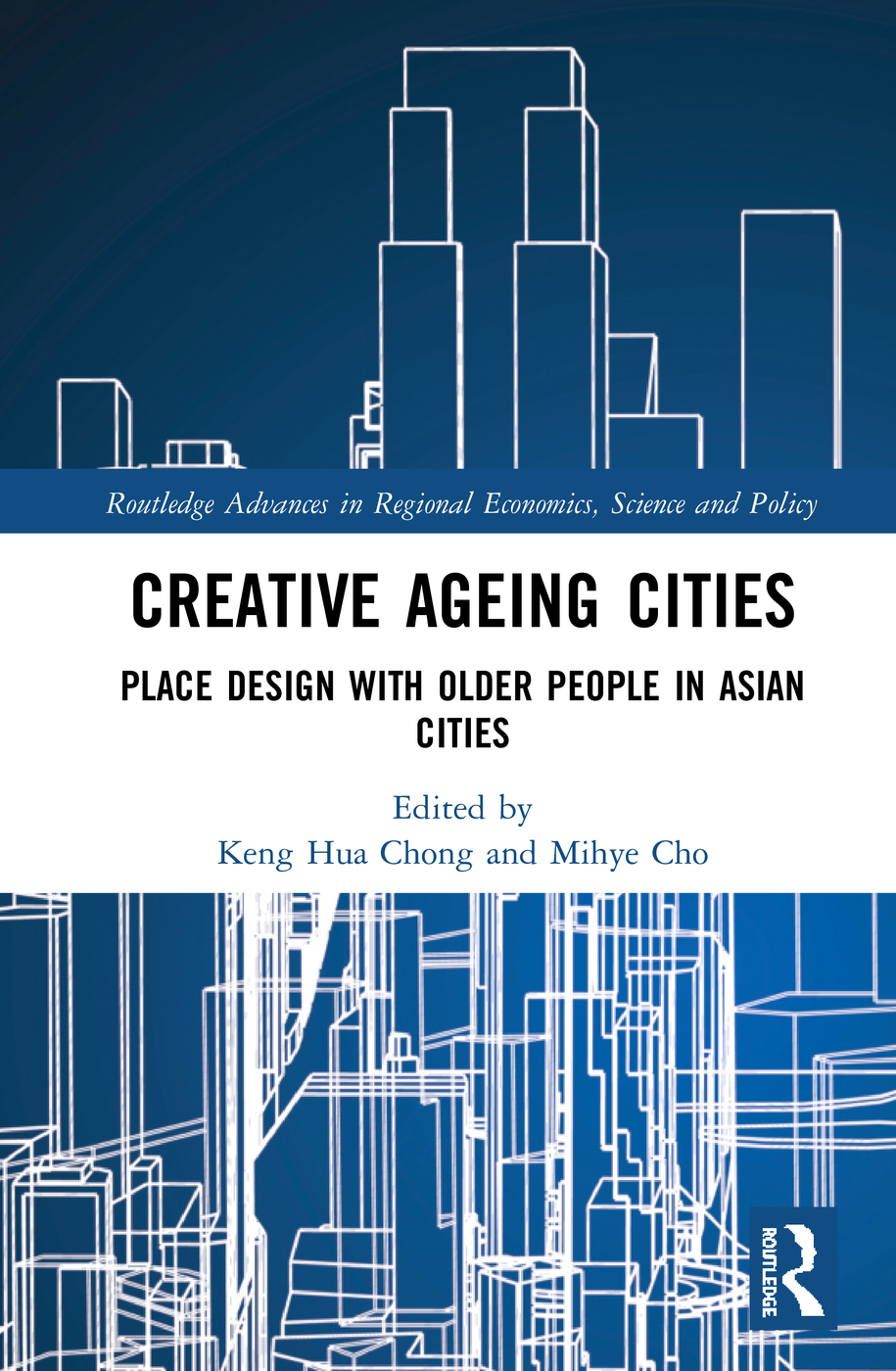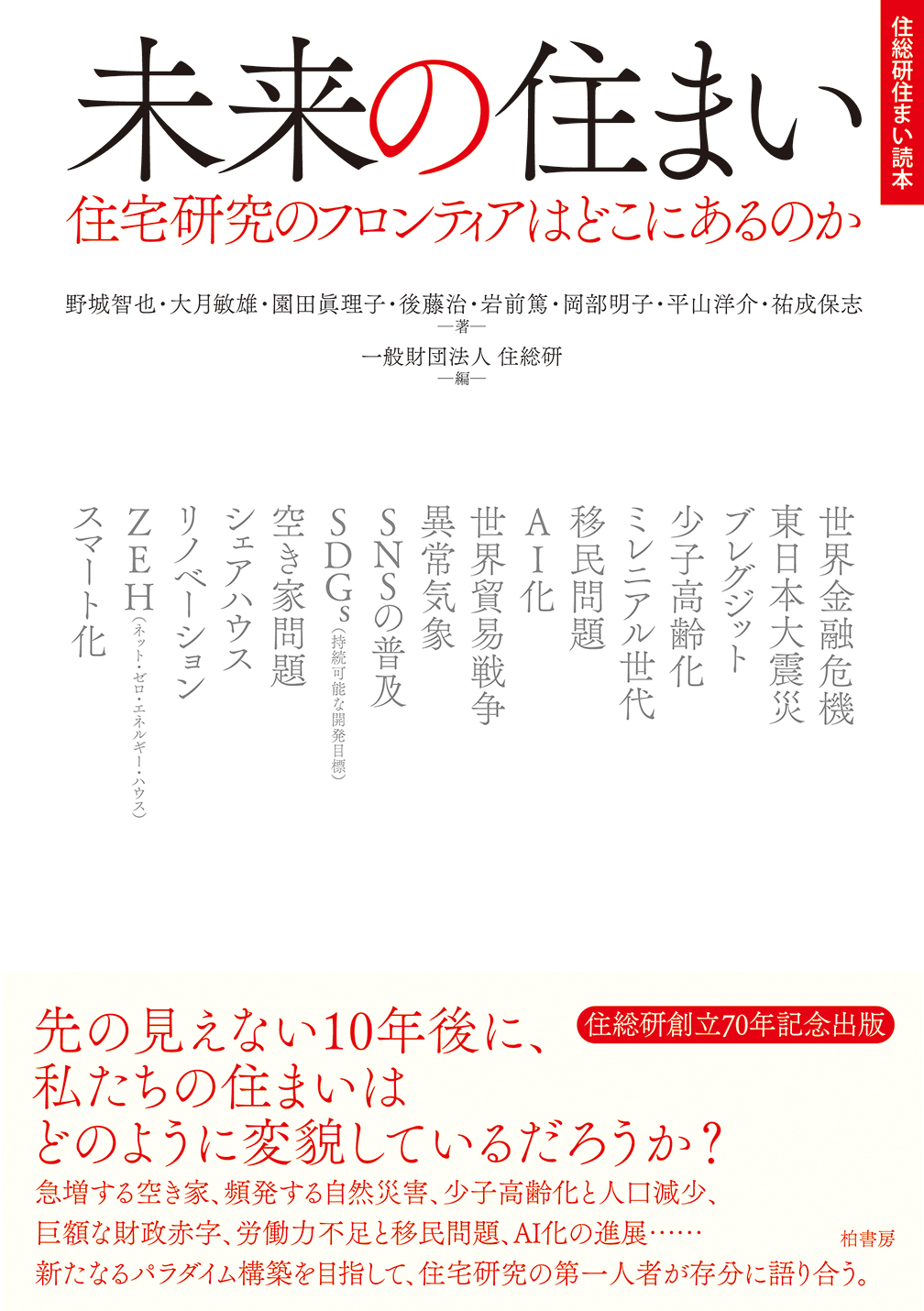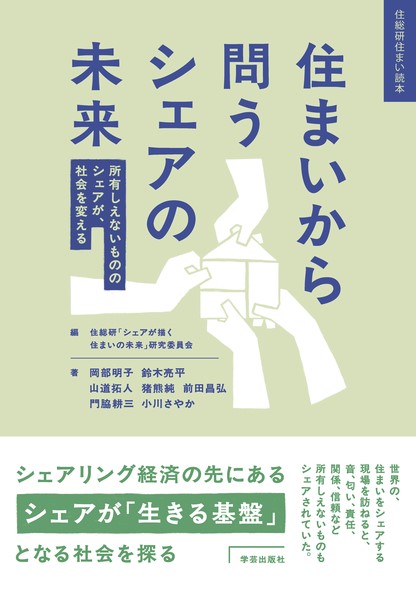本書は、2014年と2015年の2年間、日本建築学会が発行する機関誌である『建築雑誌』の編集委員会を務めた主要メンバーが中心となって編んだ本であり、評者もこのメンバーの一員であった。この『建築雑誌』という専門誌は大変由緒正しい雑誌で、1887 (明治20) 年に創刊号を発刊し、2025年1月号で通算1796号を数えている。現在、日本建築学会と称している学術団体は、1886 (明治19) 年に「造家学会」として設立され、1897 (明治30) 年に「建築学会」、さらに1947 (昭和22) 年に「日本建築学会」と改称され、現在に至っている。ちなみに、現在の東京大学工学部建築学科は、1877 (明治10) 年に工部大学校が開校し、建築家の養成のため「造家学科」が設置されたことに起源を発する。この日本初めての建築のための学科である「造家学科」関係者によって設立されたのが造家学会であった。ただし、その機関誌は1887年の創刊以来ずっと『建築雑誌』という名前なのである。
さて、篠原聡子日本女子大学教授 (現在、同学長、建築家) が建築雑誌の編集長であったときの編集コンセプトは、「住むことから考える」とういうものであった。建築物の幅は広く、小さな小屋みたいなものから、巨大超高層建築物まで各種多様に存在するのだが、突き詰めてみると、歴史的にはいずれも「住まい」にその源を発していることが多い。住まい以外の建築物は、従来住まいの中で行われていた生活行為を、外部化、専門化、集団処理化したものであると考えることもできる。それならば、改めて建築を問い直すときに、まず「住むことから考える」という問いを発することが、有効な手段の一つだと考えたためであった。
全部で24回分の『建築雑誌』の特集を考える際に、様々な角度から改めて「住まい」が議論されたのだが、議論を進めていくうちに、住まいを考えていくうえでの総合カタログのような本がないよね、という話になった。そこで、建築雑誌編集の番外編として、かつて1968年に発刊され、世界の消費文明を情報化し、相対化するという視点を人類に提供した点で一世を風靡した“Whole Earth Catalog”を目指そうということになった。
このため、「だれと住むか」「どこに住むか」「どう住むか」「設備と住む」「情報と住む」といった章からなる、「住むことを考えていくための事典」が出来上がった。通常の事典は、名詞的なカテゴリーに分けて、関連の事項が解説されるのだが、この事典は、「住む」という動詞を追究するときに生じる、いつ、どこで、どのように、といった形から「住む」という行為の広がりを認識するための、一種の認識ツールのような読み物となっている。
自分の住生活を見直してみたい、自分の家を設計してみたい、と思った際に手にとっていただけると、なるほど世の中には、こんな住み方もあるんだな、というふうに気づいていただくのが、本書の目的である。
(紹介文執筆者: 工学系研究科 教授 大月 敏雄 / 2025)
本の目次
テーマ解説
keyword 01 ひとりで住む
1 牛車で運ぶひとりの住まい(方丈庵)/2 「新陳代謝」をかたどるカプセル(中銀カプセルマンシオン)/3 nLDK から飛び出した子ども部屋(ワンルームマンション)
keyword 02 家族で住む
1 大量供給された核家族の住まい(公営住宅標準設計51C 型)/2 小さな住宅での豊かな暮らし(最小限住宅)/3 接客空間のあるマンション(70 年代の分譲マンション)/4 個の集合として家族が暮らす(武田先生の個室群住居)/5 都市の中に立体的に家族が暮らす(塔の家)
keyword 03 拡大家族で住む
1 家族の増減に合わせて伸縮する家(林・富田邸/セキスイハイムM1)/2 2 世帯住宅のその後(25 世帯住宅)
keyword 04 他人と住む
1 「お座敷」でつながる古民家の暮らし(松陰コモンズ)/2 キッチンアクセスをもつシェアハウス(SHARE 2)/3 都会的なライフスタイルをもつ大規模シェアハウス(THE SHARE)/4 コモンミールでつながる暮らし(コレクティブハウス かんかん森)
keyword 05 コミュニティの中に住む
1 住まいとしての施設(生活クラブ風の村 八街)/2 高齢化の進む団地に組み込まれたサ高住(ゆいま~る高島平)/3 多世代による空間の共有(江古田の杜プロジェクト)/4 継続的に成り立つ「街」の仕組み(シェア金沢)
column 外国人─日本社会といかに共生するか─
2章 どこに住むか
テーマ解説
keyword 01 都市に住む
1 都心の超高層マンションに住む/2 都心のペンシルビルに住む/3 都心の古マンションをセルフリノベ
keyword 02 田舎に住む
1 旧美野里町の長屋門/2 続き間100年
keyword 03 既成市街地に住む
1 長屋を建て替えながら住む(汐入)/2 谷中に住む/3 しがらみボーイズ
keyword 04 多拠点に住む
1 都心と近郊の2 拠点居住/2 夏山冬里/3 居住拠点の移動
keyword 05 移り住む
1 Arrival City/2 定期的に移り住む段ボールハウス/3 拠点化する新市街地
column 空き家─増加の背景に家族制度の変化─
3章 どう住むか
テーマ解説
keyword 01 生存のための家
1 今和次郎のバラック調査/2 今和次郎の「雪国の実験家屋」(1937)/3 プルーヴェのプレハブ住宅/4 C・プライスの「機械式住宅」/5 占領軍の家族用住宅(ワシントンハイツ)/6 岩手・住田の木造仮設住宅
keyword 02 暮らしの原点回帰
1 ライトのユーソニアンハウス/2 ガスと水道のない家(浜口ミホ)/3 「しつらい」という建築手法(清家清自邸)/4 最小限住宅の住みまし過程(池辺陽の「No71」)/5 住まいの究極のかたち(篠原一男のから傘の家)
keyword 03 新しい時代のイメージを住む
1 住宅のメールオーダー/2 大正デモクラシーの家(西村伊作)/3 グリーンベルトの家/4 Design for Living(アイソコンフラット1934)/5 新しい和洋融合(山田守自邸)/6 市場流通の部品・材料でつくられた家(イームズ・ハウス)/7 公共空間づくりの大実験(ペルー・リマハウジングプロジェクト国際コンペ1968~78)
keyword 04 終のすみか
1 グロピウス夫妻の孤高の家/2 奥村さんの素で生きる家/3 祖先の魂とともに住む(インドネシアの高床舟形住居)/4 最後に帰るところ(アスプルンドの森の墓地・追憶の丘)
column 住むことをめぐる政策─「住宅建設の20 世紀」の現在─
鼎談 いま、「住む」とは?
4章 設備と住む
テーマ解説
keyword 01 汲む・流す・洗う
1 水源から蛇口まで(給水方法)/2 排水から放流されるまで(排水方法)/3 和式から洋式へ/4 浴室のユニット化/5 洗濯機の進化
keyword 02 保存する・調理する
1 冷蔵庫とライフスタイル/2 台所の近代化 文化カマドの登場/3 今和次郎の土間の改造キッチン/4 ダイニングキッチンとステンレス流し台/5 タイマーつき電気釜
keyword 03 暖まる・涼む
1 床に熱を貯める/2 煙突効果による通風を利用する
special feature スターハウス(赤羽台団地)に見る設備の昔と未来
column 震災応急仮設プレハブ住宅─求められる住むための質向上─
5章 情報と住む
テーマ解説
keyword 01 見る・検索する
1 住まいとテレビ/2 住宅情報誌の広告/3 マンションポエム/4 不動産情報サイト/5 SNS によるデマや炎上
keyword 02 読む・行く
1 「住む」に関する新書/2 現在の住宅雑誌/3 ライフスタイル誌の分類/4 南洋堂書店の書棚/5 代官山 蔦屋書店の書棚/6 住まいのオープンハウス/7 住まいと展覧会/8 住宅展示場
keyword 03 学ぶ
1 住まいとワークショップ/2 住まいの教育/3 住まいと子どもの学び
keyword 04 編集する・建てる
1 収納用具と作法/2 DIY の生態系/3 住まいの価格/4 住まいと法規/5 住まいとBIM
column 終の住まいとしての墓─問われる人生の仕舞い方─
おわりに 対談 住みつづけるために
付録 年表─近代の「住む」を読む



 書籍検索
書籍検索