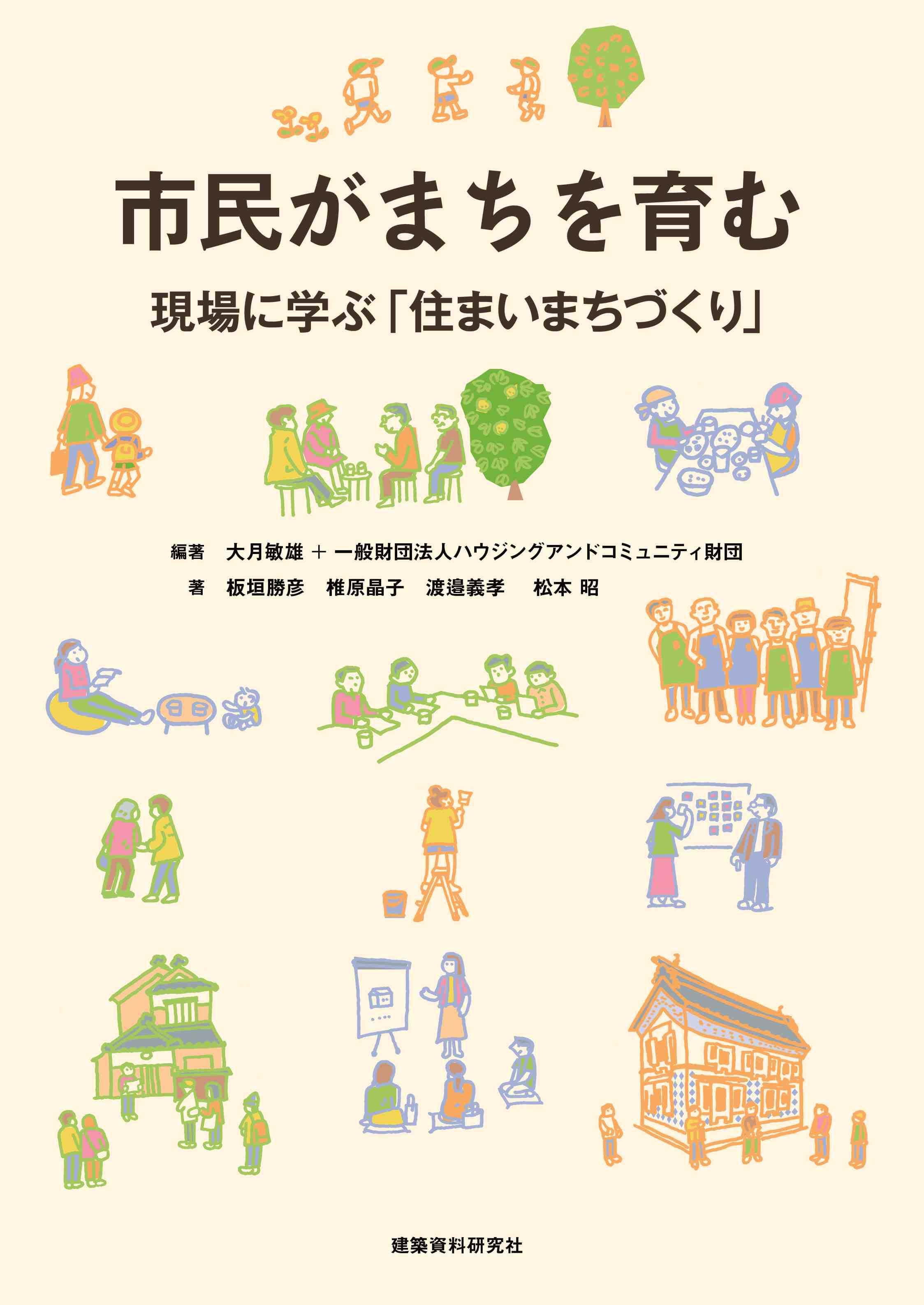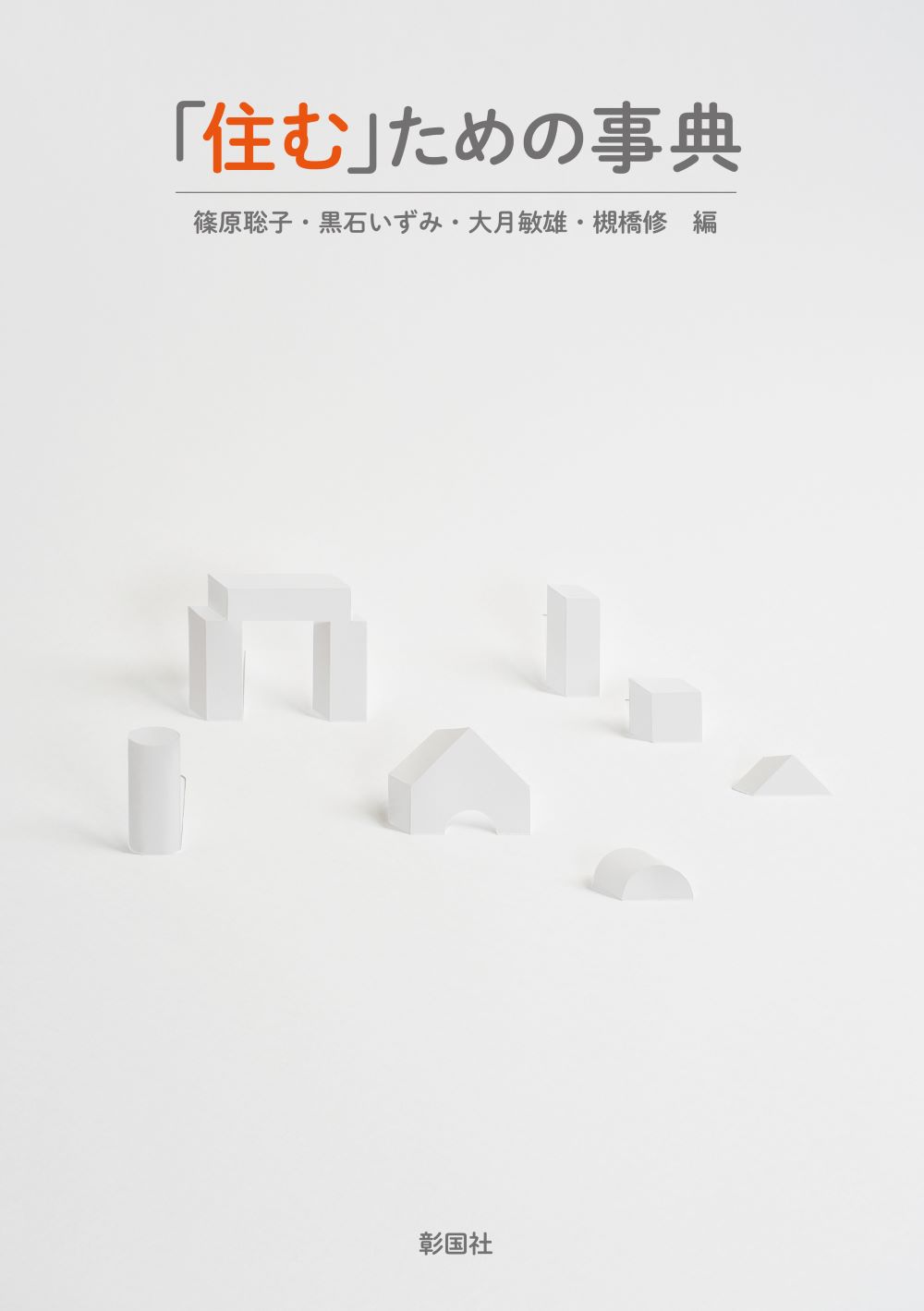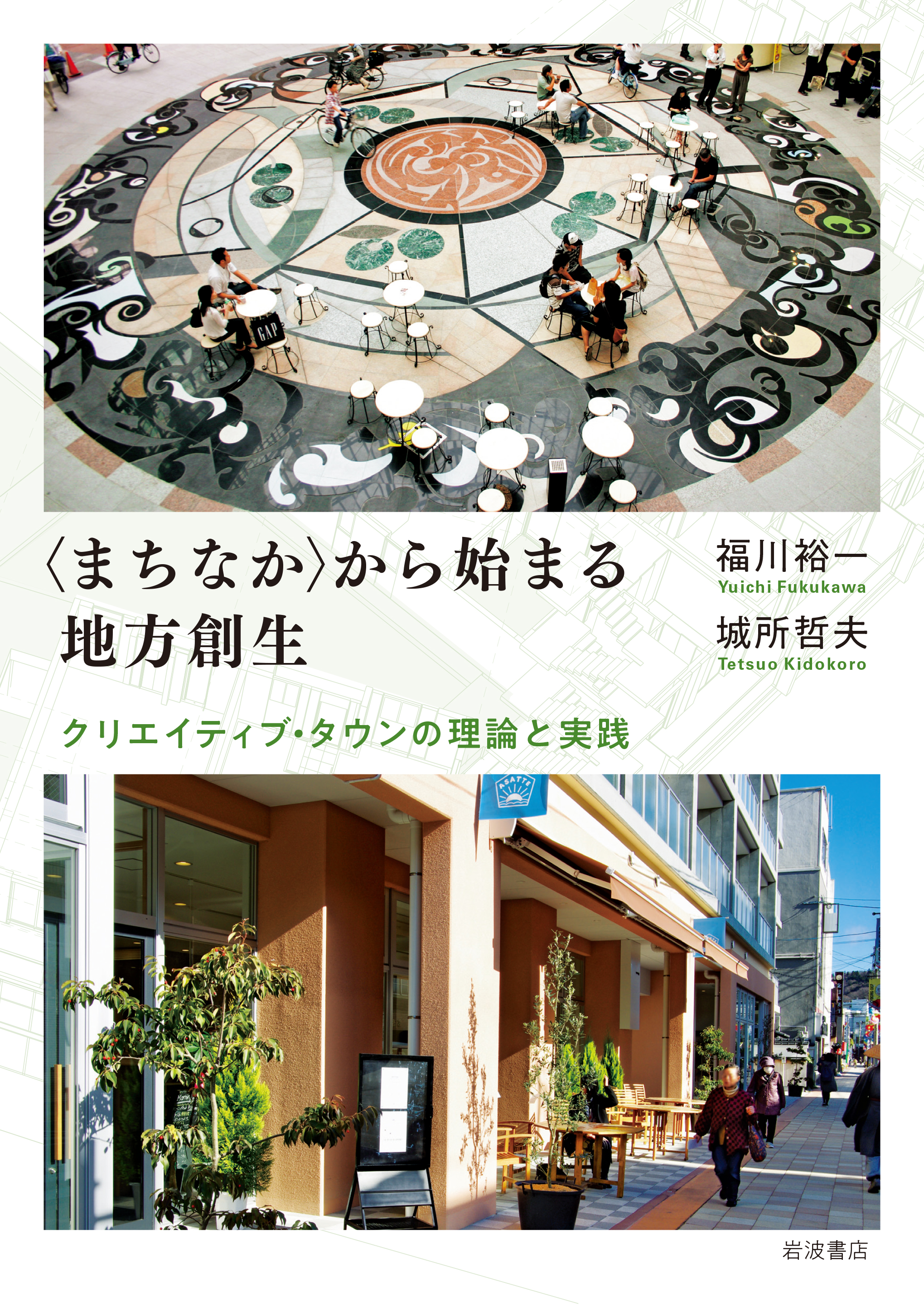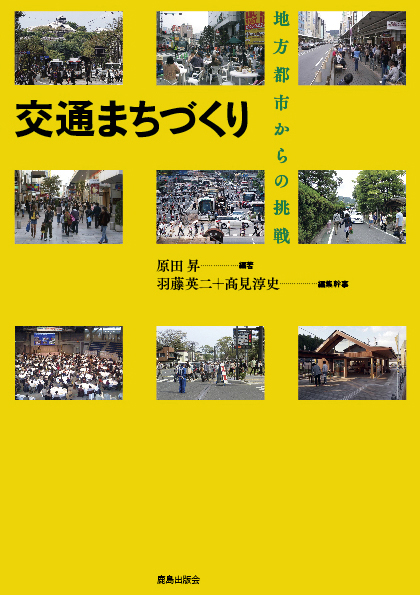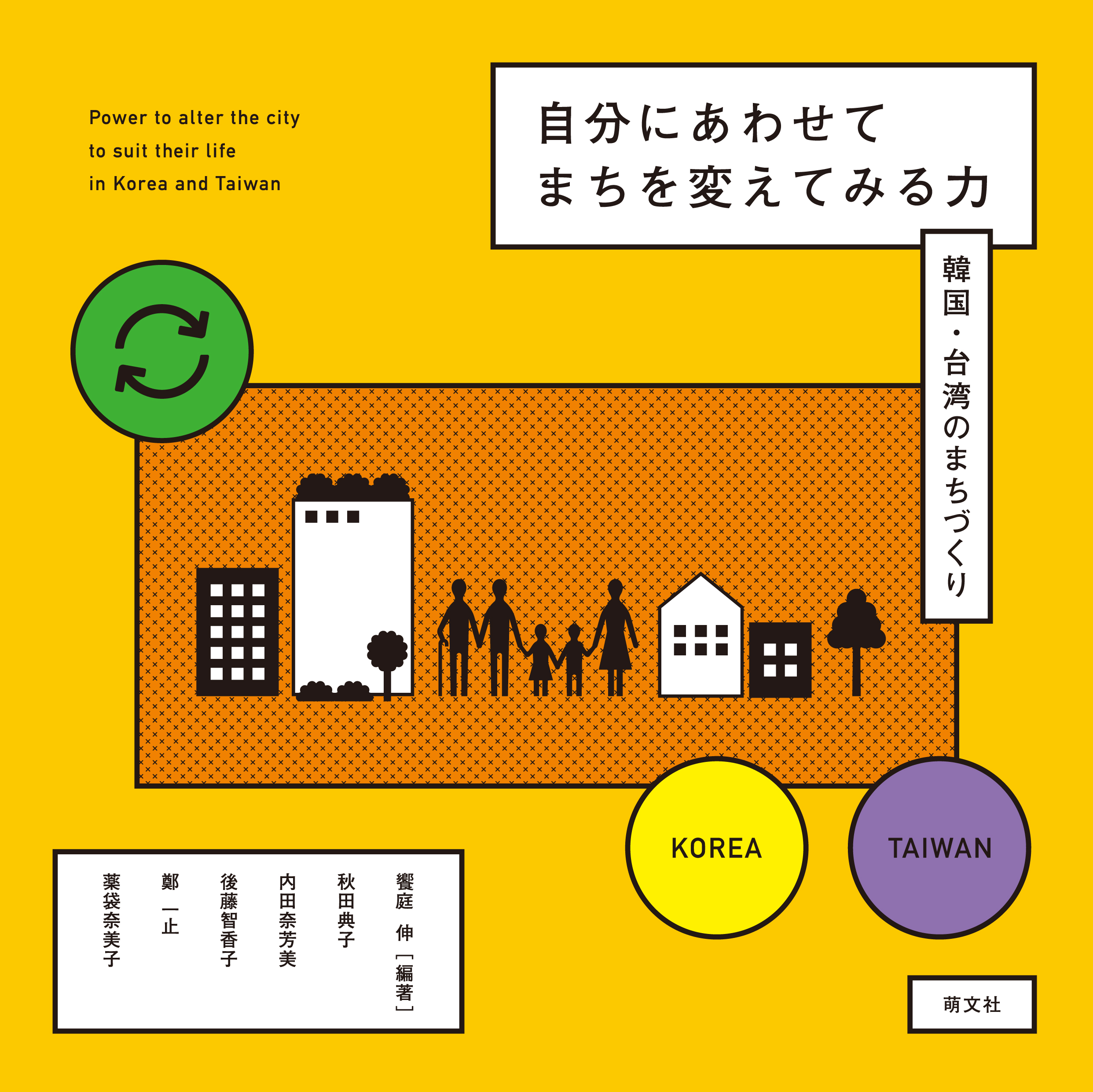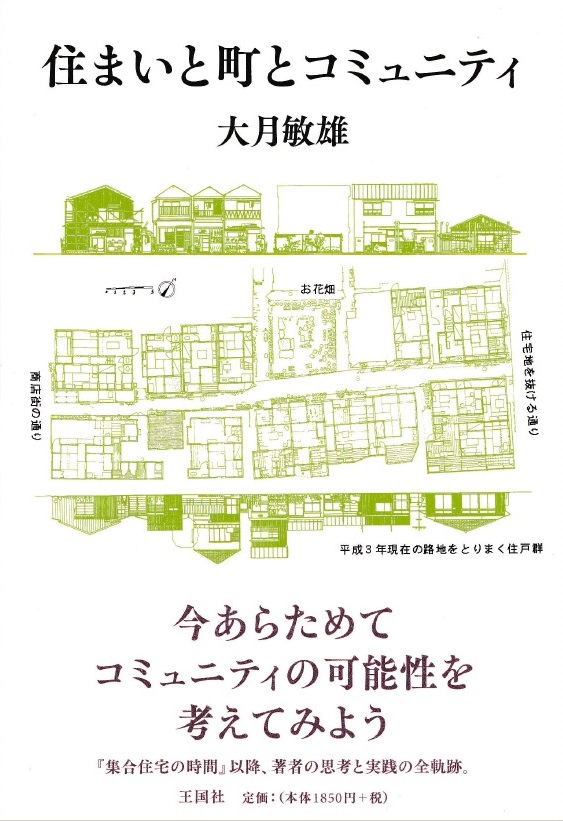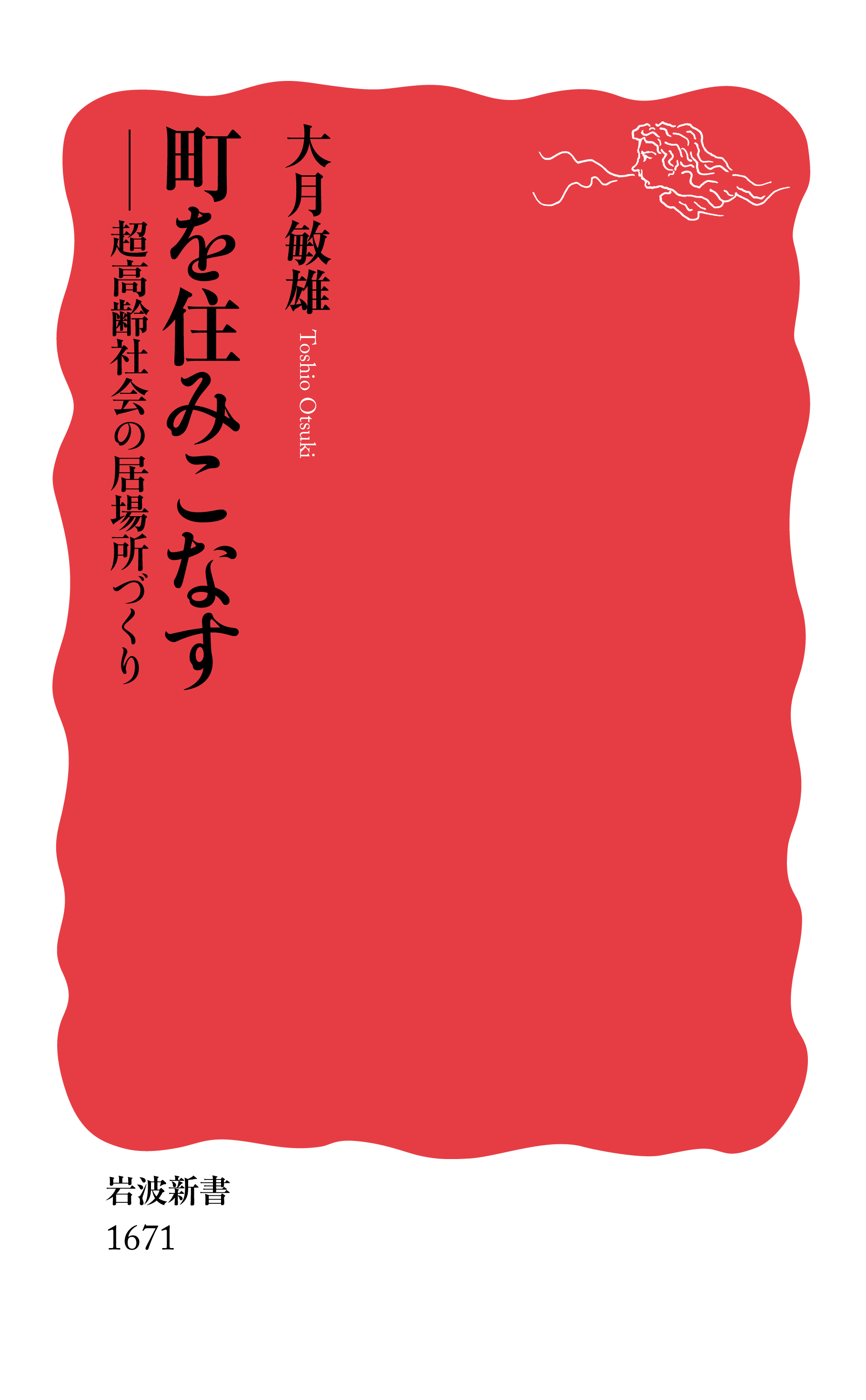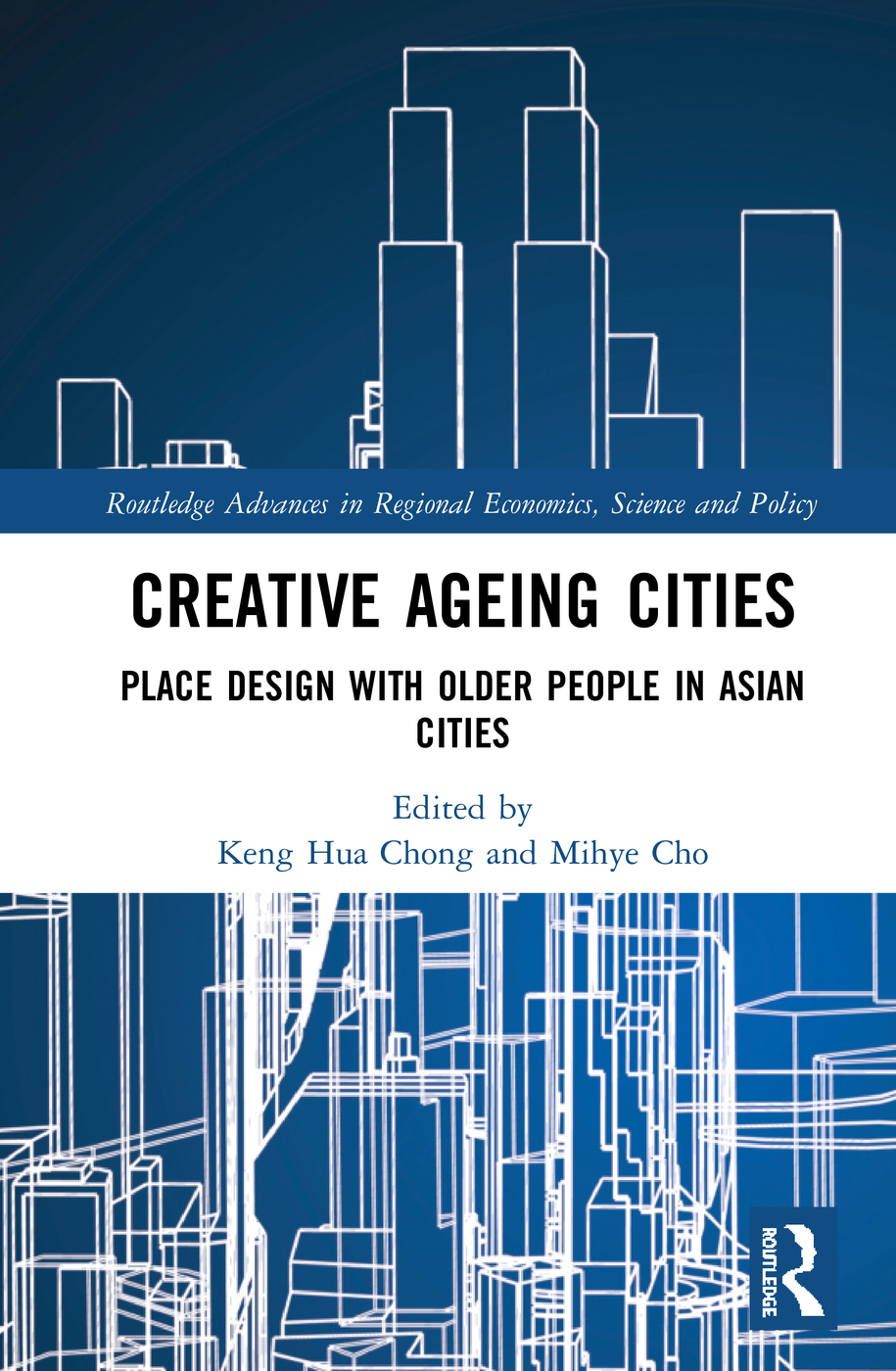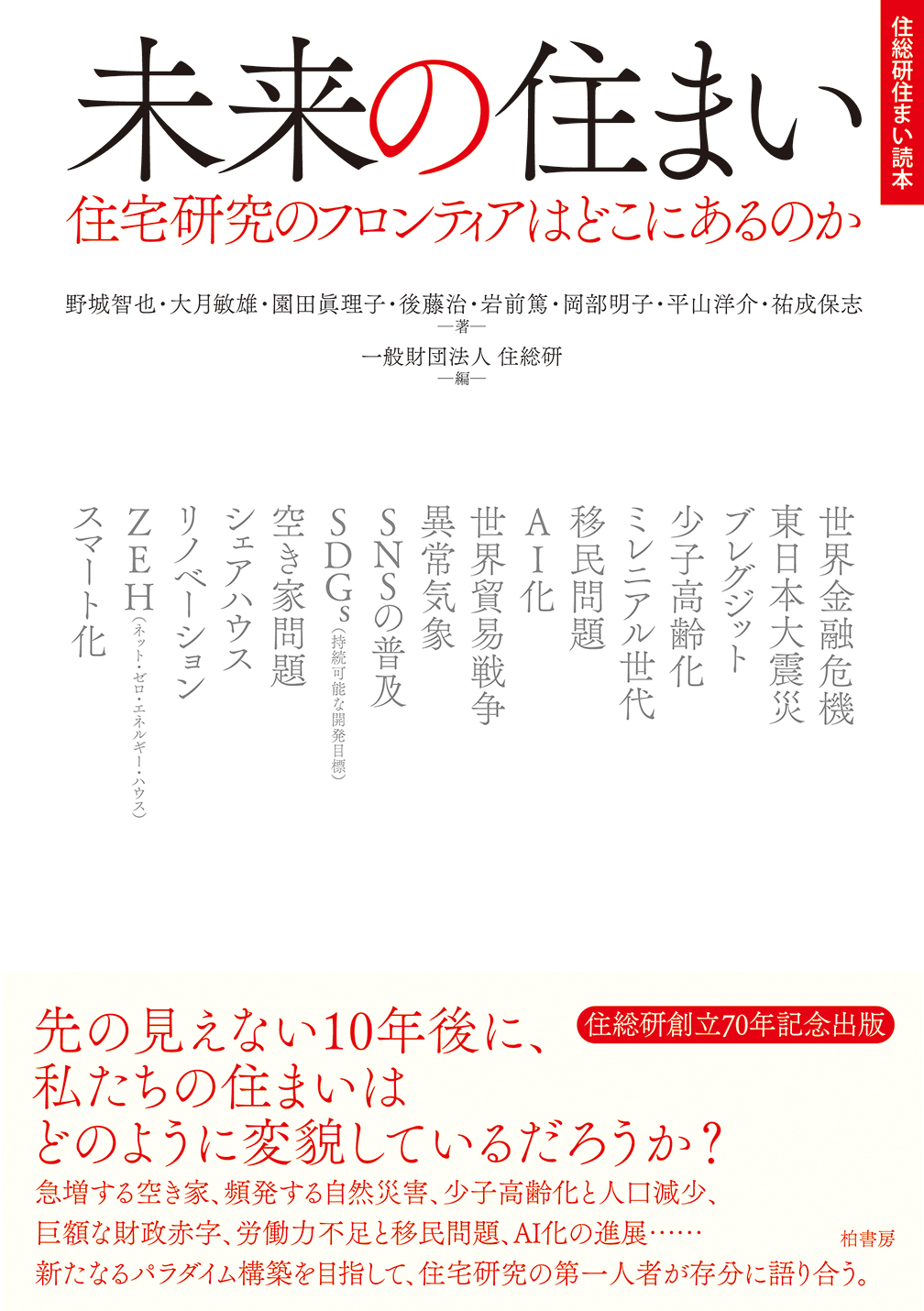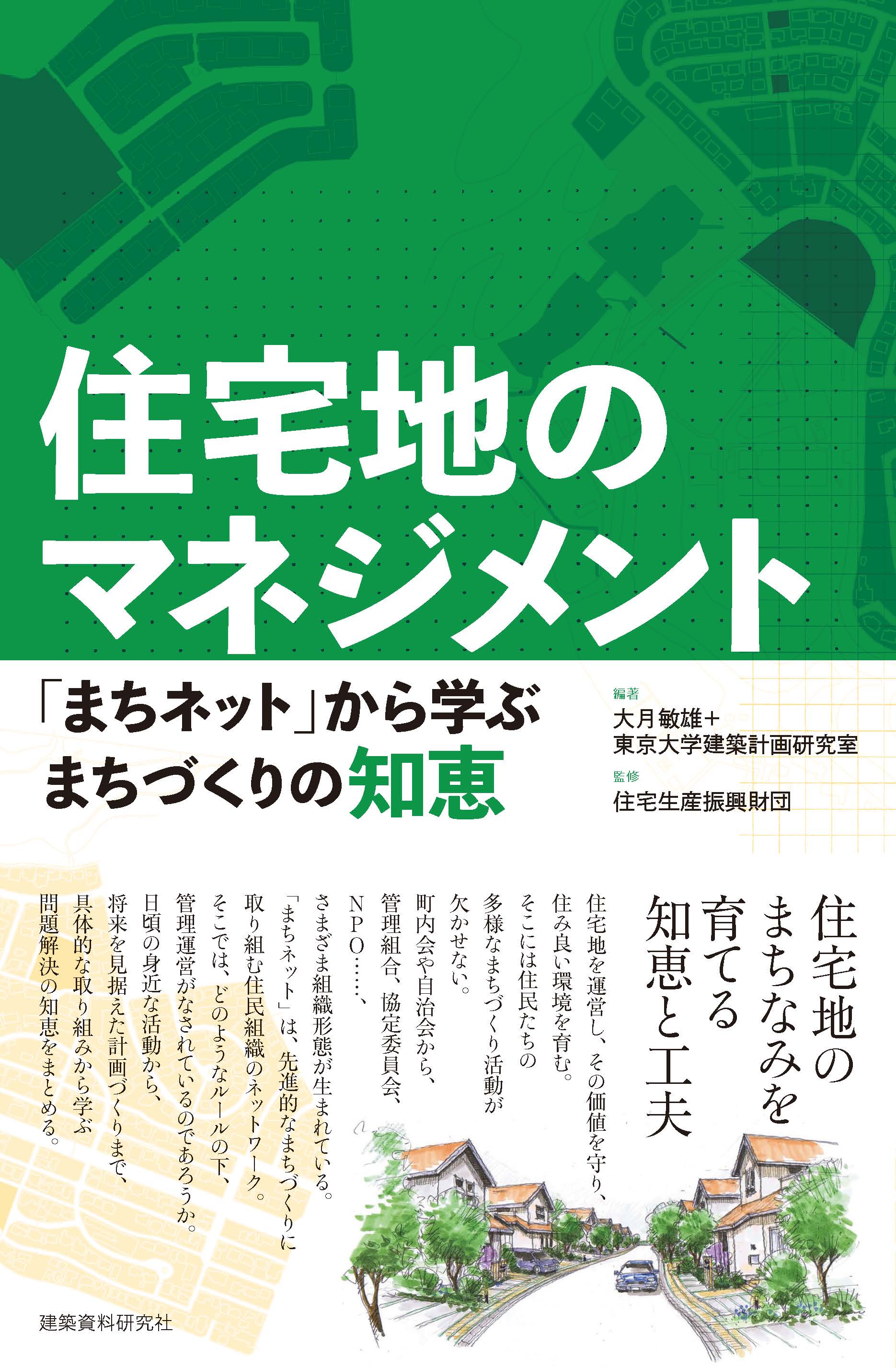
書籍名
住宅地のマネジメント 「まちネット」から学ぶまちづくりの知恵
判型など
264ページ、B5判変型
言語
日本語
発行年月日
2018年6月
ISBN コード
978-4-86358-567-6
出版社
建築資料研究社
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
「住まいのまちなみコンクール」は、住宅生産振興財団が、国土交通省の後援のもと、2005年から実施している顕彰事業である。これからは、住宅や住宅地を「住みこなす (マネジメントする)」技術も蓄積していかなければならない。そのためには、開発事業者や設計者だけが切磋琢磨するばかりではなく、住まい手にも切磋琢磨の場が必要だろう。ただ、しのぎを削って1等賞を目指す設計競技 (コンペ) というよりは、多くの経験者や知恵者が、互いのまちづくりの技を見せ合い、顕彰し合う、コンクールのような形がふさわしいだろう。というのが、この事業の企画時の議論だった。
こうして出発した「住まいのまちなみコンクール」は、戸建て住宅地を主体とした住まいのまちなみづくりに長年取り組んでいる居住者団体を対象に、その活動内容と形成されたまちなみを評価して、毎年1件の国土交通大臣賞と、4件の住まいのまちなみ賞を授与し、かつ、5つの受賞団体に対して、3ヶ年にわたり活動経費の支援を行うというプログラムとして出発し、2018年で第14回目を迎えた。
さらに、「まちコン」授賞式の場を借りて、全国のまちなみづくりに取り組む居住者団体が、おのおのの経験や知恵を、フラットに交換できる場づくりのために、「まちコン」受賞団体の同窓会である「住まいのまちなみネットワーク (通称: まちネット)」をつくり、毎年新規団体の「授賞式」に合わせて「総会」を開くということにしたのである。もちろん、総会のあとの「懇親会」の方が、重要な役割をもっている。
このように、「まちコン」から「まちネット」が生まれ、受賞団体同士の知恵の交換のきっかけができたのはよかったが、当初から気になっていたのが、こうした知恵が、これからまちづくりに取り組もうとしている居住者団体に、どうしたら届けられるのかということであった。受賞団体のその後の活動の様子を伺いに行くと、まさに目から鱗が落ちるようなアイデアや知恵がたくさん聞けるのだが、自分だけがそれを聞くのではもったいない。しかし、よく考えると、世の中には、自分が町内会長や自治会長になったときに、あるいは住宅地の運営に携わる羽目になったときに、参考にすべき教科書はない。それなら一層のこと、まちコン受賞団体が経験されてきた数々の知恵をテキストのようなものにして、たとえ明日、町会長の順番が回って来ようと、この一冊を読めば大丈夫、というようなものがつくれないだろうか、ということに思い至り、改めて10年分の受賞団体50組織に、聴き取り調査をお願いしてできたのが、本書である。
(紹介文執筆者: 工学系研究科 教授 大月 敏雄 / 2019)
本の目次
住宅地のマネジメント 大月敏雄 東京大学教授
受賞50団体一覧
I・問題解決の知恵
1 まちの構成と組織の運営
1-1 まちの空間構成とわかりやすさ
1-2 居住者の構成とまちの人材
1-3 役員の確保
1-4 新旧役員の引き継ぎ
1-5 委員会と適材適所
1-6 資金・資源の調達
2 他の組織・人材との連携
2-1 同じ住宅地内の組織連携
2-2 近隣組織との連携
2-3 ボランティア組織との連携
2-4 NPO法人との連携
2-5 行政との連携
2-6 さまざまな専門家と相談する
2-7 専門家としての開発事業者
2-8 大学研究者との連携
3 情報共有
3-1 定期刊行物
3-2 情報共有の手段
3-3 ITを駆使する
3-4 気持ちを共有するための仕組み
3-5 新規居住者への情報伝達
4 人々を巻き込む
4-1 多様な人を巻き込む
4-2 子どもを巻き込む
4-3 ボランタリーな活動が
4-4 まずは居場所づくりから
4-5 不加入者問題
5 活動の動機づけ
5-1 楽しいイベントとの抱き合わせ 68
5-2 コンテストと顕彰
5-3 来街者のまなざしがモチベーション
5-4 まちの課題をまちの魅力に変える
5-5 まちの宝物探しと愛着づくり
5-6 まちの記憶と記録
5-7 新しい伝統をつくり出す
5-8 蝶や蛍の飛び交うまちに
6 合意形成
6-1 アンケートを活用
6-2 実測値を活用
6-3 情報共有と意見交換の場
6-4 少しずつ意見を挙げていく
6-5 説得力のある説得術
7 安心安全
7-1 安心安全設計
7-2 備えあれば憂いなし(防犯)
7-3 ついでに防犯
7-4 備えあれば憂いなし(防災)
7-5 ITを使った防災
7-6 高齢者の安心
8 まちを美しく
8-1 清掃
8-2 ゴミ集積所
8-3 植栽管理の共同性
8-4 植栽管理の持続性
8-5 修景
9 公共私の境を超えた活動
9-1 近隣の緑地を活かす
9-2 道路をつくり管理する
9-3 公園をつくり管理する
9-4 隣地の開発から守る
9-5 私有地の管理
9-6 空き家という地域財産を活かす
10 まちなみのルールと計画
10-1 建築協定・緑地協定の運営を確実に
10-2 建築協定・緑地協定の運営をやりやすく
10-3 建築協定・緑地協定の変更・更新
10-4 景観条例
10-5 独自のまちなみルール
10-6 地域に即したルール
10-7 基礎情報と将来計画
II・「住まいのまちなみコンクール」受賞団体の活動
01 スウェーデンヒルズ(北海道当別町)
02 新屋参画屋(秋田県秋田市)
03 諏訪野(福島県伊達市)
04 七日町通り(福島県会津若松市)
05 中央台鹿島三区(福島県いわき市)
06 フィオーレ喜連川(栃木県さくら市)
07 オーナーズコート守谷(茨城県守谷市)
08 光葉団地(茨城県稲敷市)
09 真壁(茨城県桜川市)
10 南平台(茨城県阿見町)
11 旭ヶ丘(茨城県筑西市)
12 こしがや・四季の路(埼玉県越谷市)
13 佐倉染井野(千葉県佐倉市)
14 布佐平和台(千葉県我孫子市)
15 碧浜(千葉県浦安市)
16 たい歴(東京都台東区)
17 城南住宅(東京都練馬区)
18 埴の丘(東京都町田市)
19 三輪緑山(東京都町田市)
20 ガーデン54(東京都日野市)
21 フォレステージ(東京都日野市)
22 青葉美しが丘(神奈川県横浜市)
23 山手(神奈川県横浜市)
24 ニコニコ自治会(神奈川県藤沢市)
25 みずき(石川県金沢市)
26 滝呂(岐阜県多治見市)
27 桂ケ丘(岐阜県可児市)
28 蒲原宿(静岡県静岡市)
29 グリーンヒル青山(滋賀県大津市)
30 新海浜(滋賀県彦根市)
31 西竹の里(京都府京都市)
32 桂坂(京都府京都市)
33 姉小路(京都府京都市)
34 新千里南町3丁目(大阪府豊中市)
35 コモンシティ星田(大阪府交野市)
36 アルカディア21(兵庫県三田市)
37 ワシントン村(兵庫県三田市)
38 尾崎(兵庫県赤穂市)
39 オナーズヒル奈良青山(奈良県奈良市)
40 いんしゅう鹿野(鳥取県鳥取市)
41 木綿街道(島根県出雲市)
42 矢掛宿(岡山県矢掛町)
43 グリーンヒルズ湯の山(愛媛県松山市)
44 土居廓中(高知県安芸市)
45 青葉台ぼんえるふ(福岡県北九州市)
46 コモンライフ新宮浜(福岡県新宮町)
47 百道浜(福岡県福岡市)
48 パークプレイス(大分県大分市)
49 木花台(宮崎県宮崎市)
50 大城花咲爺会(沖縄県北中城村)
附・「住宅地のマネジメント」のために知っておきたい用語 大月敏雄
住宅地の開発と計画
概説:都市計画と住宅地開発の展開
近代都市計画の系譜/都市計画/土地区画整理事業/住宅地開発
まちなみの骨格
概説:まちなみを支えるインフラ
法律上の道路/宅地割り/コモン/歩車共存/緑の計画
まちなみのルール
概説:まちなみづくりの制度
景観形成の手法/まちなみの協定と地区計画/まちなみ保存/景観法
居住者組織とマネジメント
概説:日本のコミュニティ
居住者組織/管理組合
新たなマネジメント領域
概説:多様化社会を乗り切る知恵
ライフスタイル/住宅政策と福祉/住宅のストック化と流通/安心安全/環境との共生/新技術
関連情報
第31回住生活月間協賛・まちなみシンポジウム―財団40周年記念―「まち・いえ・人のつながりを育む~住み継がれていくコミュニティとは」 ((一財)住宅生産振興財団、日本経済新聞社 2019年10月21日)
https://book.gakugei-pub.co.jp/event-33829/
【基調講演】大月敏雄「住宅地のマネジメント - 住みこなせる町づくり」
https://www.machinami.or.jp/pdf/symposium/31_otsuki_kichou_panel.pdf



 書籍検索
書籍検索