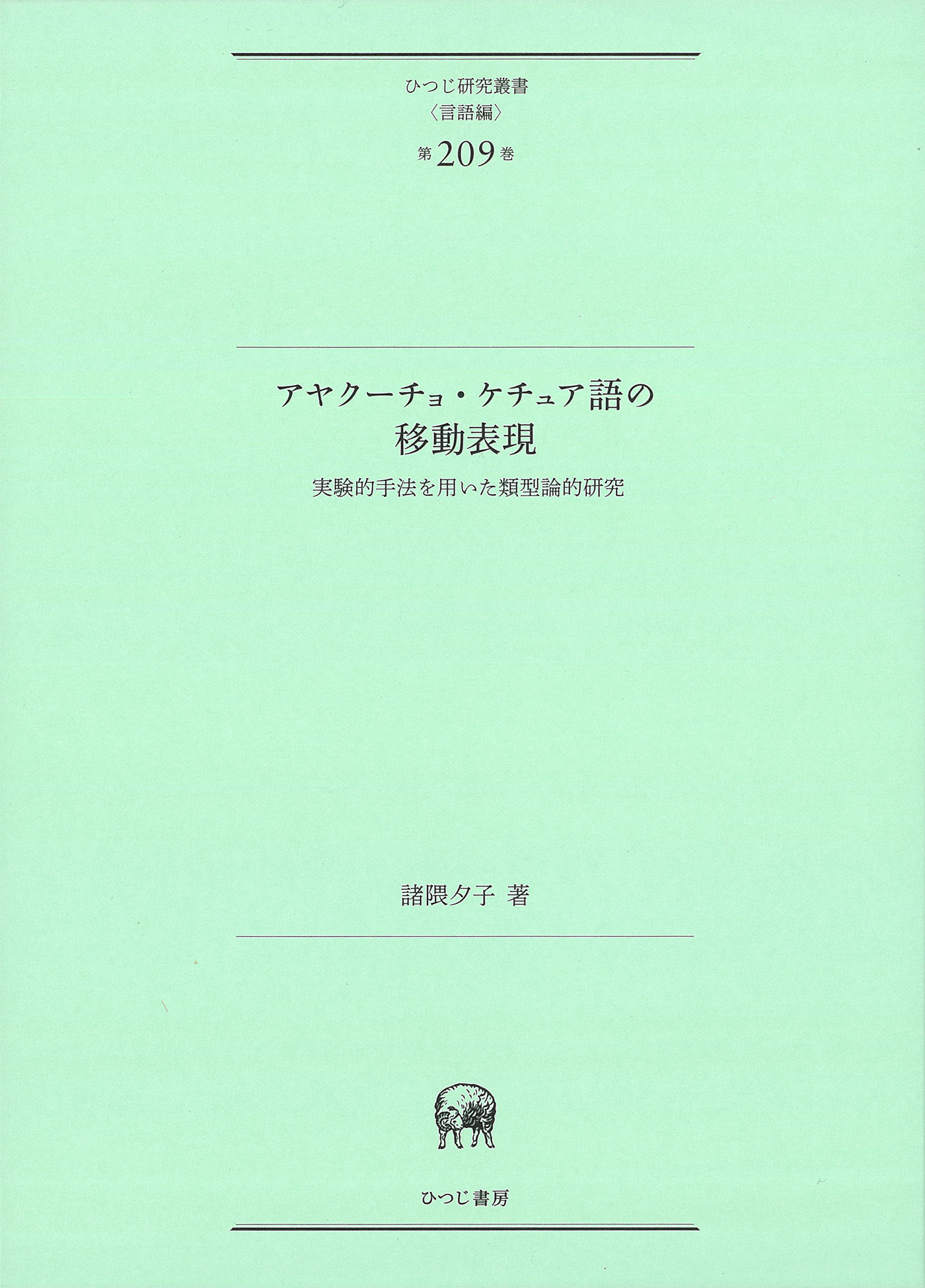
書籍名
ひつじ研究叢書(言語編) 第209巻 アヤクーチョ・ケチュア語の移動表現 実験的手法を用いた類型論的研究
判型など
316ページ、A5判
言語
日本語
発行年月日
2025年2月
出版社
ひつじ書房
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
本書のテーマはケチュア語の移動表現を中心とした文法記述である。ケチュア語は、南米大陸西部、アンデス地域の先住民言語であるケチュア語族の言語の総称である。現代におけるケチュア語はスペイン語に次ぐこの地域のリンガ・フランカであり、先住民のアイデンティティを象徴する重要な存在となっている。日本においてケチュア語は、学術的には主にアンデス地域研究における媒介言語として注目されているほか、日常生活においても、アンデス地域の音楽を通じて当地域の言語文化に興味を持つ愛好者が数多く見られる。
本書はケチュア語の一変種であるアヤクーチョ・ケチュア語 (ISO 639: quy) の文法を概説しつつ、移動表現を網羅的に記述したものである。移動は我々人間にとって非常に身近な現象であり、「歩く」「上る」「落ちる」といった移動を表す表現は言語や文化の違いを超えて日常的に用いられる基本的な表現である。一方で、こうした移動の概念を表現する方法―例えば、「上への移動」を表す固有の動詞があるのか?前置詞や接辞などを使うのか?―は言語ごとに異なり、類型論的に興味深い様相を見せる。 (実際に、日本語と英語では前述の点で大きく異なっている)
こうした移動表現の研究は近年の調査・分析技術の発展により国内外で続々と成果の発表が行われており、本書がこの世界的潮流に新たな一石を投じることを期待している。さらに本書の内容はケチュア語の体系的・俯瞰的な文法記述、移動表現の網羅的記述の両側面において本邦で初のものであり、日本における言語学のみならずアンデス地域研究、さらに異文化交流にも貢献できれば幸甚である。
本書では、アヤクーチョ方言の移動表現の類型論的特徴として以下の 3 点を主張している。 i) この言語は、移動物がたどる経路を主動詞とそれ以外の要素で同時に、つまり余分に表す傾向が非常に強い言語である。 ii) この言語の移動表現は、移動物が移動する方法―自律的に動くのか、何かに動かされるのか、はたまた疑似的に動いているように見なされるのか―によって異なる特徴を見せる。 iii) この言語の移動表現は、移動物がたどる経路の種類―例えば、上るのか、下るのか―によって異なる特徴を見せる。
さらにこの言語の個別言語的特徴として、次の3点を主張する。 i) アヤクーチョ・ケチュア語において、経路を表示する手段の文法性の高さは、それが表す経路の種類の幅広さと対応している。 ii) 動詞 pasa <通る> は、経路を表す動詞の中では特異的に幅広い種類の経路を表すことができる。 iii) 動詞接尾辞 -yku は従来指摘されている <中へ> <下へ> に限らず、幅広い種類の経路の表現に用いることができる。
以上の記述・分析は、移動表現の国際共同研究プロジェクト Motion Event Description across Languagesで共有される実験的手法を用いたフィールドワークに基づいている。この手法を用いることにより、世界で初めてアヤクーチョ・ケチュア語の特徴を各表現が使われる文脈を明確にしながら記述するとともに、他の言語と統一的な観点で比較し、類型論的特徴を網羅的・体系的に論じることが可能になっている。
(紹介文執筆者: 諸隈 夕子 / 2025年9月29日)
本の目次
第2章 アヤクーチョ・ケチュア語
第3章 調査方法
第4章 A実験:アヤクーチョ・ケチュア語の移動表現の全体的特徴
第5章 C実験:経路タイプによる移動表現の多様性
第6章 アヤクーチョ・ケチュア語の経路表示の個別言語的特徴
第7章 結語
関連情報
第5回東京大学而立賞受賞 (東京大学 2024年)
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/research/systems-data/n03_kankojosei.html
論文賞 (日本言語学会 2023年度)
諸隈 夕子 ケチュア語アヤクーチョ方言の示差的目的語標示と情報構造 『言語研究』163号pp.111-138 (2022年9月)
https://ls-japan.org/work/award/awd2023/
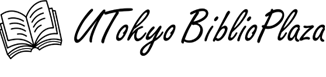



 eBook
eBook