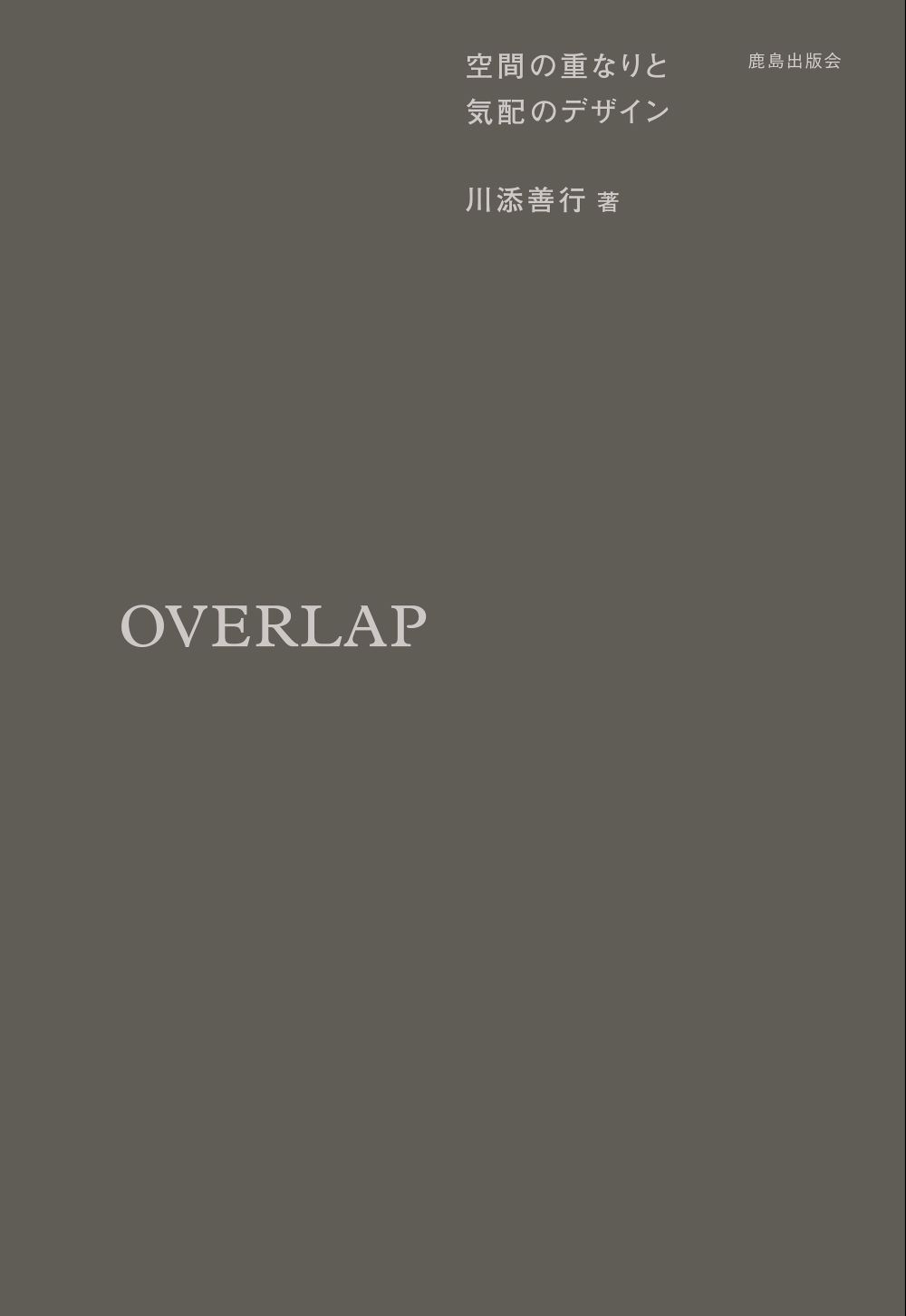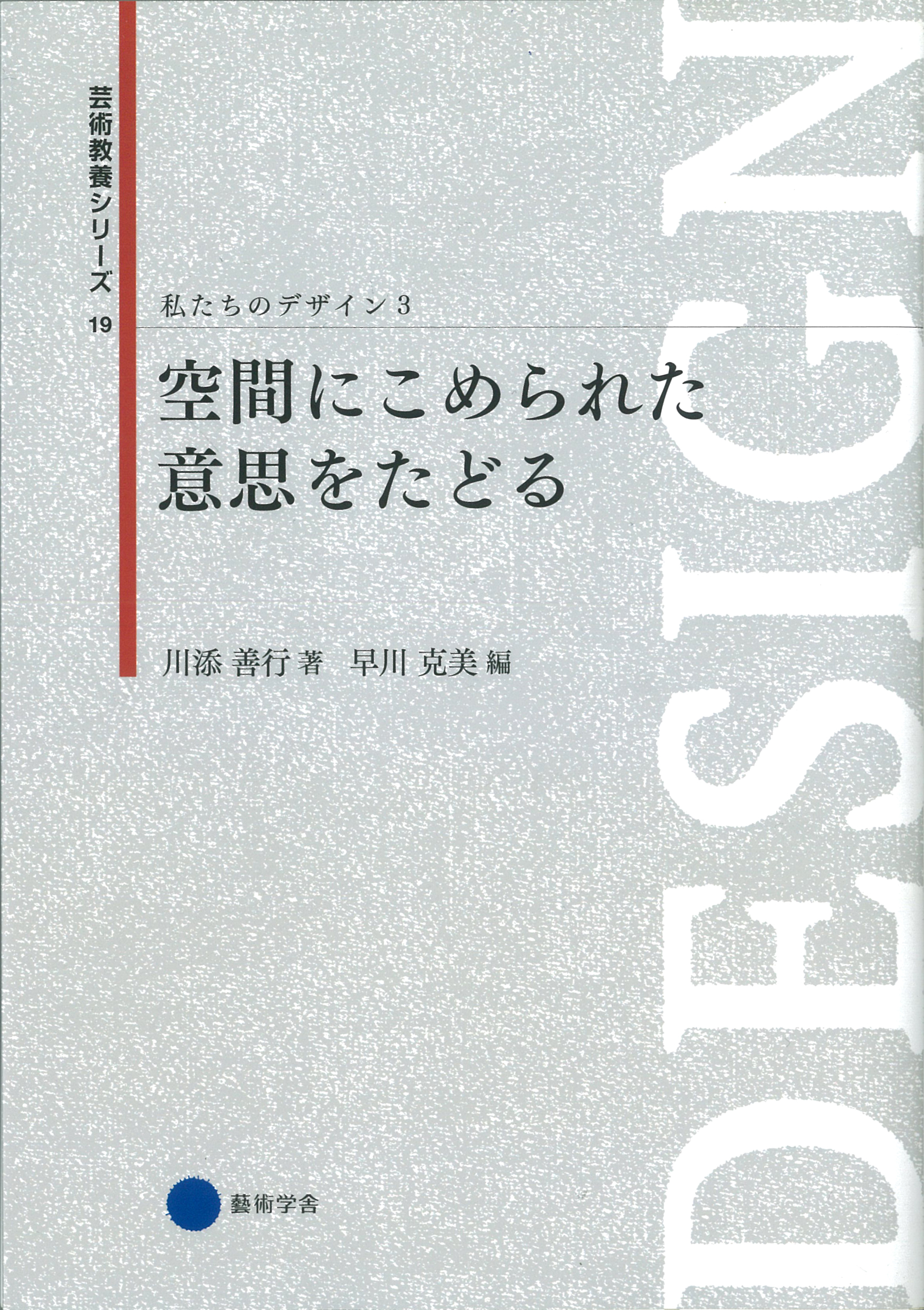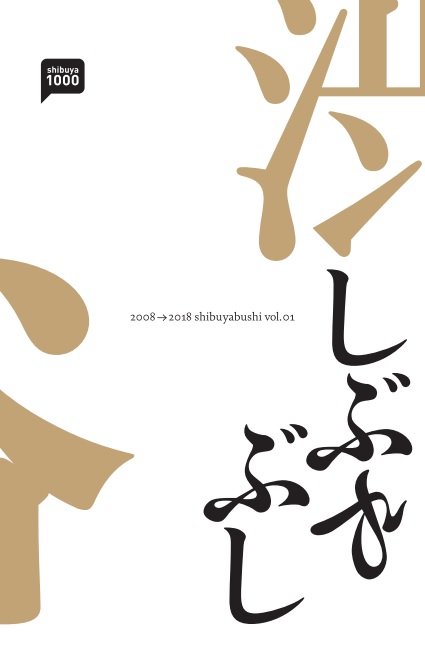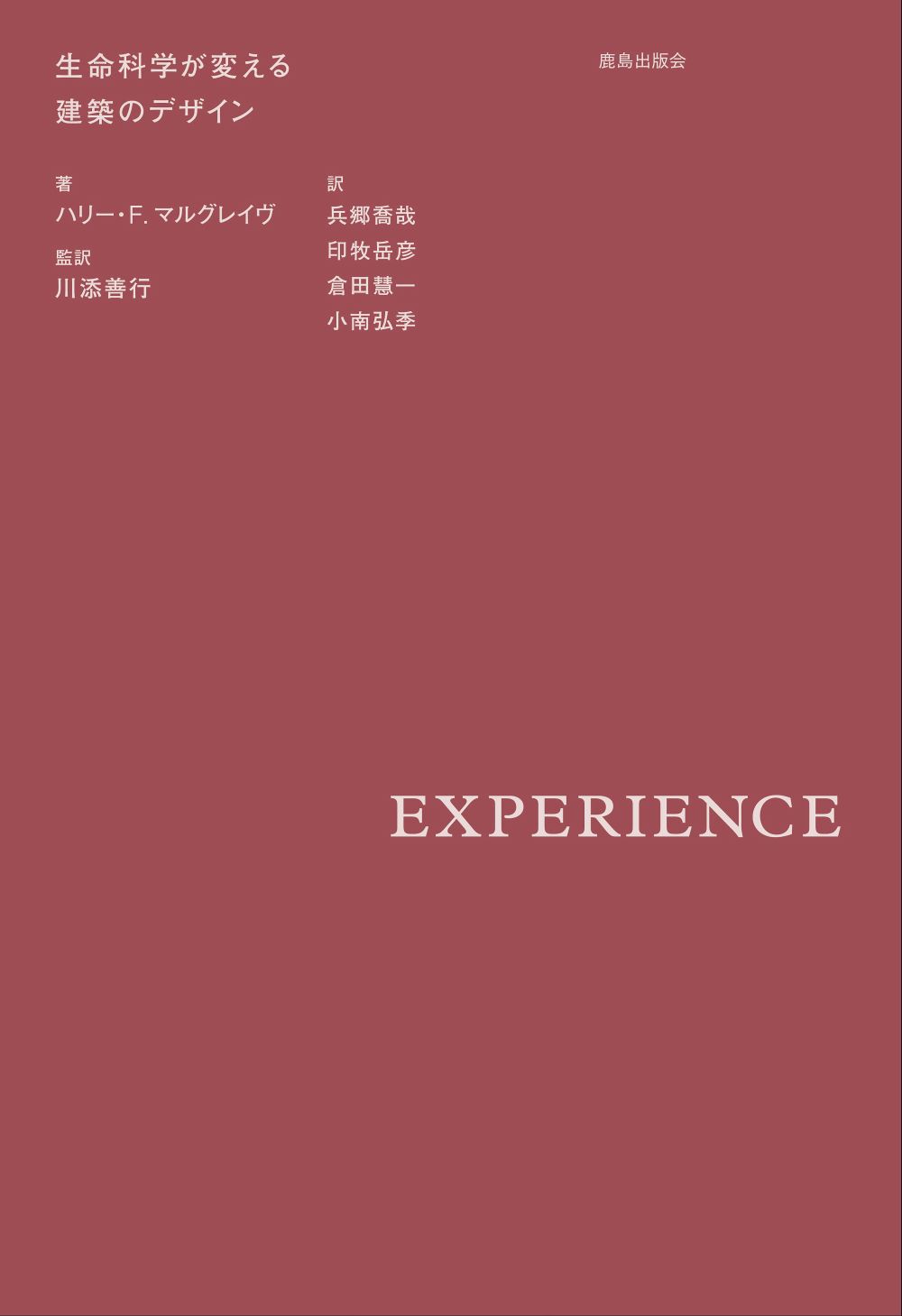
書籍名
EXPERIENCE 生命科学が変える建築のデザイン
判型など
408ページ、四六判
言語
日本語
発行年月日
2024年1月
ISBN コード
9784306047099
出版社
鹿島出版会
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
本書は、建築を生み出す作り手の側の視点で建築を論じるのではなく、近年、進歩がめざましい生命科学の知見を用いることで、建築を認知する際のメカニズムを深く考察し、建築を体験する側の視点から建築を論じるという歴史的展開の書です。たしかに、これまでの歴史を振り返っても、体験する側の視点で建築論全体を組み立て直そうという試みは皆無であったということができるでしょう。その意味で、生命科学の知見を用いて、もう一度人間を中心に建築を論じる試みは、まるでルネサンスのような転回の幕開けを宣言する書であると言えるかもしれません。
原題は、『From Object to Experience: The New Culture of Architectural Design』といい、著者のハリー・フランシス・マルグレイヴ (HARRY FRANCIS MALLGRAVE) は、現代における非常に重要な建築史家の一人です。
本書は、建築物の経験に関する考え方の歴史と、神経科学、認知科学、進化生物学などの分野から得られた最新の知見を組み合わせることで、建築デザインの本質と未来の文化について論じています。本書には、デザインコンセプトを高らかに主張する「オブジェクト」から、人間の内面を深く洞察することによる「体験」へとデザインの主題を変えるべきだというマルグレイヴの主張が込められています。建築家でヘルシンキ工科大学名誉教授でもあるユハニ・パッラスマーは、「本書は、建築を美学的なオブジェクトとしてではなく、心理的リアリティや経験からアプローチすることへの関心が現在高まっている中で、独創性に富んだ将来性のある文献である。」と評しています。
私の研究室でも、脳波をはじめとした生体反応によって建築を評価するという研究を進めています。建築意匠という美しさやカッコ良さを考える分野の議論が、誰かの主観にのみ頼っているのが学生の頃からずっと引っかかっていたため、空間を感じる時の脳の反応を科学的に調べることで、「カッコ良い」をもっとオープンに定義できないかと考えたからです。そのため、私は日常的に脳科学の文献を読むことが多く、すっかり本書が建築書であることを忘れてしまいそうになりました。それほど、最新の脳科学の研究成果を体系的にまとめています。
脳科学の研究は、私たちが空間をどのように認知しているかを明らかにしつつあります。例えば、より高い天井の空間や開放性のある空間を美しいとみなす傾向があることが明らかになっています。さらに、別の研究によると、視覚だけではなく、五感を通して空間を認識している具体的なメカニズムがわかってきました。これらはすべてここ数年のできごとです。脳科学の分野はまさに日進月歩で、新しい知見が日々生まれています。こうした知見を用いることで、マルグレイヴは建築を視覚芸術として捉える従来の見方の限界を指摘し、嗅覚や聴覚を含めた五感を総動員して認識するものへと、具体例を示しながらその定義を書き換えようとしています。ちなみに、視覚に関する研究についても、鋭角なかたちと曲線のどちらを人が好むのか、中心視野と周辺視野の体験としての違いなど、これまでの私たちの常識が、生命科学の知見によって、あっという間に塗り替えられていく体験を読者の皆さんはすぐに経験することになるでしょう。
(紹介文執筆者: 生産技術研究所 准教授 川添 善行 / 2025)
本の目次
序 章
第1章 文化の実践としての建築
第2章 文化理論と生物学
第3章 生命体と環境
第4章 新たな知覚モデル
第5章 美の体験
第6章 形態と空間
第7章 場所・空気感・ディテール
第8章 社会性の起源
第9章 デザインの新たなエートス
サラ・ロビンソンによる序文 建築家は文化をつくる サラ・ロビンソン
訳者あとがき
関連情報
『OVERLAP』『EXPERIENCE』刊行記念川添善行連続対談企画「本と本が語り合う」
https://kajima-publishing.co.jp/overlap/
建築理論のゆくえ
加藤耕一(建築史家・東京大学教授)×川添善行 (東京大学工学部1号館3階講評室 2024年5月1日)
https://kajima-publishing.co.jp/overlap/event1/
社会学と建築のオーバーラップ
南後由和(社会学者・明治大学准教授[現 法政大学教授])×川添善行 (紀伊國屋書店新宿本店3階アカデミック・ラウンジ 2024年5月29日)
https://kajima-publishing.co.jp/overlap/event2/
個と全体のクロスオーバー
高橋祥子(ジーンクエスト代表取締役)×川添善行
https://kajima-publishing.co.jp/overlap/event3/
アーバニズムと建築
泉山塁威(日本大学准教授・ソトノバ共同代表理事)×西田 司(建築家・東京理科大准教授)×川添善行 (大橋会館2Fラウンジ 2024年6月19日)
https://kajima-publishing.co.jp/overlap/event4/
私たちの未来
内藤 廣(建築家・東京大学名誉教授・多摩美術大学学長)×川添善行 (東京大学工学部1号館15号講義室 2024年7月16日)
https://kajima-publishing.co.jp/overlap/event5/
書評:
加藤耕一 評「建築体験と知覚モデル――建築デザインが生み出す快楽・情動・幸福感」
https://kajima-publishing.co.jp/books/architecture/7fmux3vsbi/#review
岡本章大 評 Book Review (『建築士』Vol.73, No. 863 2024年8月)
https://www.kenchikushikai.or.jp/data/kaishi/2024/2024.08-2.pdf
書籍紹介:
印牧岳彦 (『REPRE』Vol.51 2024年6月30日)
https://www.repre.org/repre/vol51/books/translation/4/
研究室紹介:
研究室紹介|東京大学川添研究室 (Kawazoe Lab 東京大学川添研究室 | YouTube 2024年3月19日)
https://www.youtube.com/watch?v=xzbgGOHpn_g



 書籍検索
書籍検索