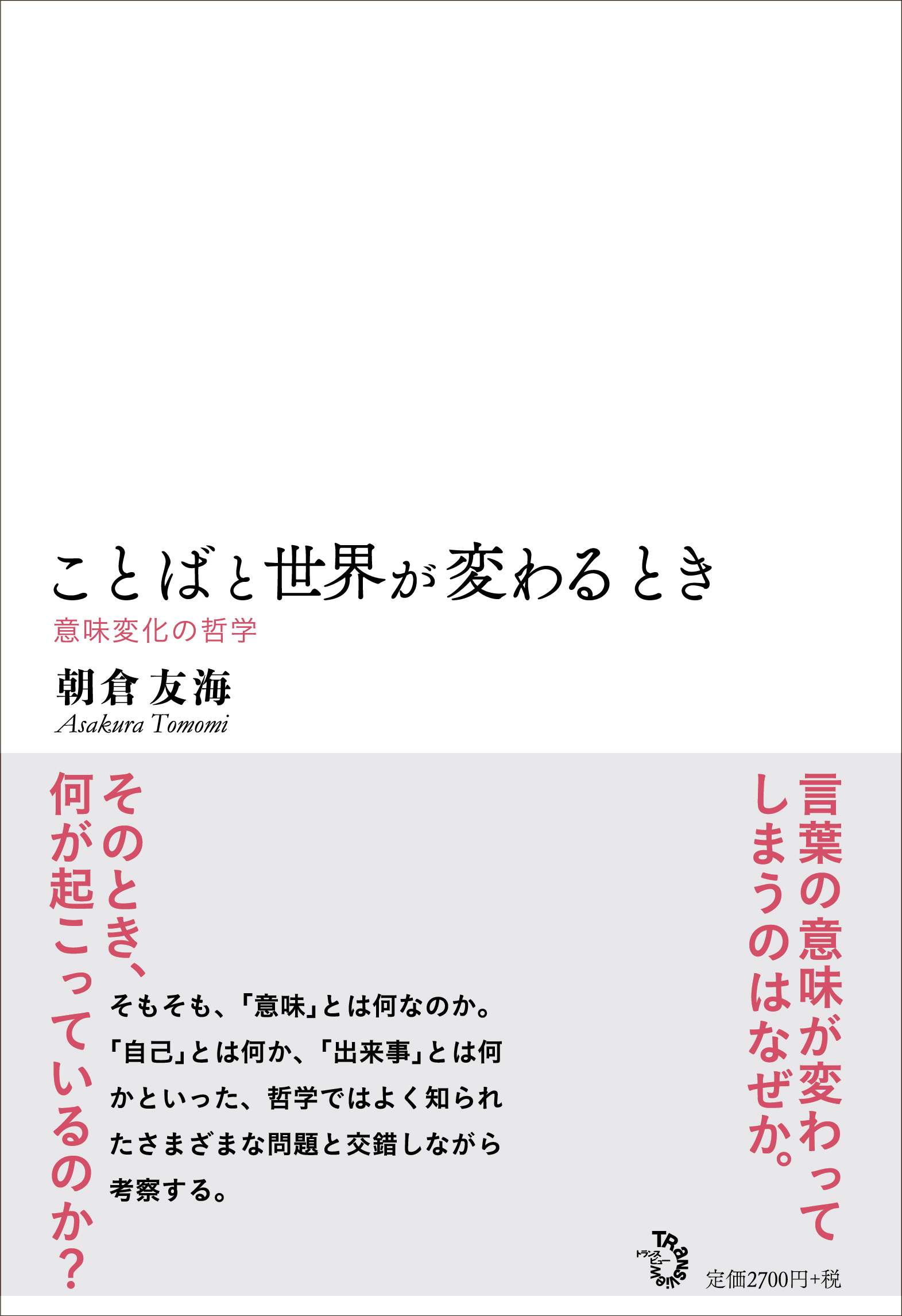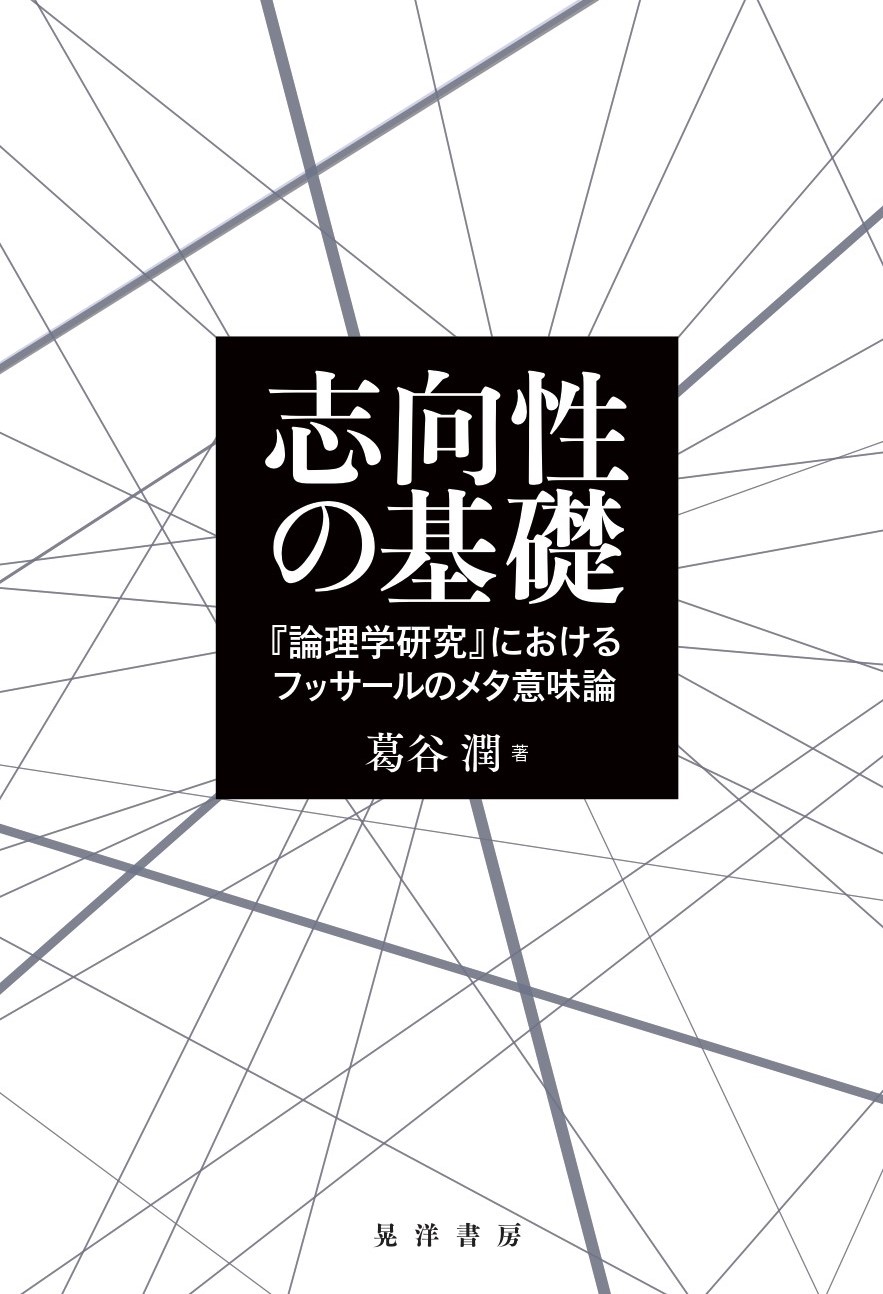言語哲学の目的は、言葉の使用、およびそれに関わる様々な現象 (まとめて「言語現象」と呼ぼう) を理解することである。ただし、伝統的な言語哲学は、言語現象の中でも、言葉による「知識」(情報) の伝達が「うまくいく」仕組みの解明に主眼を置いてきた。そのため、言語哲学者たちは様々な「理想化」(単純化) のもとで会話を考察してきた。たとえば、「会話の参加者は知識の共有を共通の目的とする」や「言葉の意味は一定であり、参加者に共有されている」といった想定である。この種の理想化は、言葉の基本的な働きを理解するうえで一定の有用性をもち、実際に豊かな成果を生み出してきた。しかし、このような想定が成り立つのは、せいぜい教室でのやり取りのような、いわば「行儀のよい」会話に限られる。フェイクニュースや言葉による抑圧といった「言葉の悪用」をはじめ、社会的・倫理的な問題に直結する多様な言語現象を理解するためには、このような理想化から逸脱した状況で何が起こるのかに目を向ける必要がある。
近年、行儀のよい会話を越えて、実社会の言葉の問題に既存の言語哲学の知見を応用しようとする「応用言語哲学」と呼びうる運動が盛り上がりを見せている。本訳書の原著であり、言葉の悪用に焦点を当てた言語哲学の入門書であるHerman Cappelen & Josh Dever の Bad Language (Oxford University Press, 2019) もまた、このような運動の中に位置づけることができる。
本書で扱われる主題は多様である——言葉の悪用 (嘘やミスリード、でたらめ、言葉による抑圧など) や悪い言葉 (蔑称、差別語、罵倒語) の使用に加え、総称表現に関連する誤謬推理、性的同意に関する問題、SNSにおける「ライク」や「エモート」の使用に伴う課題、知識伝達以外の言葉がもつ影響 (語彙効果) 等々。本書はこれらを「理想化からの逸脱」という切り口から整理したうえで、それぞれの本性と、その「悪さ」の所在について、言語と関連する限りで論じていく。ただし、本書は独自の見解の論証を目指すものではなく、むしろこれらの論点を考察する際に知っておきたい概念的ツールや既存の見解を、簡潔かつ中立的に紹介することを目指すものである。
蔑称の使用を例に取れば、本書では次のような問いが議論される。蔑称はどのような意味内容をもつのか。その内容はどのように相手に伝わるのか (それは「言われていること」なのか、それとも「前提されていること」なのか)。また、蔑称の使用が人を傷つけるのは、そのような意味内容 (だけ) によるのか、それとも話し手の態度の表出によるのか、あるいはその語に結びついた歴史的事実などによるのか。さらに、蔑称は罵倒表現など他の「悪い言葉」とどのように異なるのか、等々。このような問いが、「前提」や「表出」といった概念的ツールの簡潔な導入とともに、「記述内容説」、「前提説」、「表出説」、「禁止説」などの立場を紹介する形で論じられる。
本書は言葉の悪用に対処する具体的な解決案や指針を提供するものではない——そのような解決案はおそらくまだ誰も持ち合わせていないし、またそれを得るには哲学のみならず倫理学や法学、社会学、心理学などの知見を横断する学際的な協働が重要になるだろう。しかし、そのような解決案や指針を模索するうえで、問題となる言語現象に対する深い理解は確かに有用 (場合によっては不可欠) であるはずだ。本書は、そのような理解を目指す分野、すなわち応用言語哲学への優れた手引きである。
(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 助教 葛谷 潤 / 2025)
本の目次
序
第一章 理想化されたコミュニケーション
1─1 七つの典型的な理想化
1─2 手持ちの道具を確認し、実社会に立ち戻る
1─3 いくつかの但し書き
1─4 本書の概要
第二章 言葉を非理想的に使う三つの方法
2─1 逸脱した意図:会話的推意
2─2 なぜ推意にかかずらうのか
2─3 逸脱した意味─前提
2─4 逸脱したスコアボード─文脈のコントロール
2─5 逸脱的なものから悪いものへ
第三章 真理をぞんざいに扱う
3─1 偽なことを述べる
3─2 嘘とミスリード
3─3 真理を尊重することはすべてのコミュニケーションにとって根本的なのか
第四章 でたらめと根深いでたらめ
4─1 でたらめ
4─2 嘘、ミスリード、でたらめからフェイクニュースへ
4─3 根深いでたらめ(つまり、ナンセンスな、意味不明な言葉)
第五章 概念工学
5─1 概念工学への導入:私たちは言葉が何を意味するかを気にかける
5─2 概念工学の主論証(および小史)
5─3 概念工学者にとってのいくつかの課題
第六章 蔑称
6─1 導入
6─2 記述内容説
6─3 前提説
6─4 表出説
6─5 禁止説
6─6 まとめ
第七章 語彙効果
7─1 語彙効果を導入する:言葉の非認知的・連想的効果
7─2 非認知的語彙効果:いくつかの実例
7─3 公の場での議論や理論的研究における語彙効果の利用
7─4 語彙効果の一般理論
7─5 語彙効果はなぜ言語哲学でほとんど無視されてきたのか
第八章 総称文と欠陥のある推論
8─1 導入:総称文とは何か
8─2 総称文の振る舞いについてより詳しく
8─3 いくつかの興味深い実験
8─4 総称文:意味と認識の交わり
8─5 要約
第九章 理想的でない言語行為
9─1 導入
9─2 分散した聞き手
9─3 分散した話し手
9─4 デジタル時代の言語行為
第一〇章 言葉による抑圧と言葉による声の封殺
10─1 言語行為とは何か:手短な導入
10─2 言語的抑圧
10─3 ポルノグラフィーによる言語的抑圧
10─4 声を封殺すること
第一一章 同意という言語行為
11─1 同意の典型例:家の訪問、医療処置、同意書、セックス
11─2 同意に関するいくつかの問い
11─3 暗黙の同意の不精密さ/曖昧さ
11─4 欺きは同意を無効にしうるか
11─5 同意を動的に捉える
11─6 理想化がどのようにして失敗するのかを示す例としての同意
第一二章 言語の理想理論と非理想理論について考える
12─1 理想化された理論はばかげているのか
12─2 予測とガリレイ的理想化
12─3 理解とミニマリストの理想化
12─4 理想化によって何を取り除くべきか
12─5 社会科学における理想理論と非理想理論
12─6 言語の理想理論と非理想理論
訳者解説
1.イントロダクション
2.理論的理想化からの逸脱としての悪い言葉
3.応用言語哲学と言語哲学のこれから
訳者あとがき
参考文献
索引
関連情報
Herman Cappelen and Josh Dever著『Bad Language - Contemporary Introductions to Philosophy of Language』 (Oxford University Press 2019年3月刊)
https://global.oup.com/academic/product/bad-language-9780198839644
あとがきたちよみ:
あとがきたちよみ 『バッド・ランゲージ ――悪い言葉の哲学入門』 (勁草書房編集部ウェブサイト『けいそうビブリオフィル』 2022年10月12日)
https://keisobiblio.com/2022/10/12/atogakitachiyomi_badlanguage/
書評:
和泉悠 (南山大学人文学部准教授) 評 (『図書新聞』3582号 2023年3月11日号)
https://toshoshimbun.com/product__detail?item=1703316323918x437063985485640800
イベント:
藤川直也×和泉悠 「言葉のダークサイドに抗う」 『バッド・ランゲージ 悪い言葉の哲学入門』(勁草書房) 刊行記念 (本屋B&B 2023年1月27日)
https://bookandbeer.com/event/230127a_bad-language/



 書籍検索
書籍検索


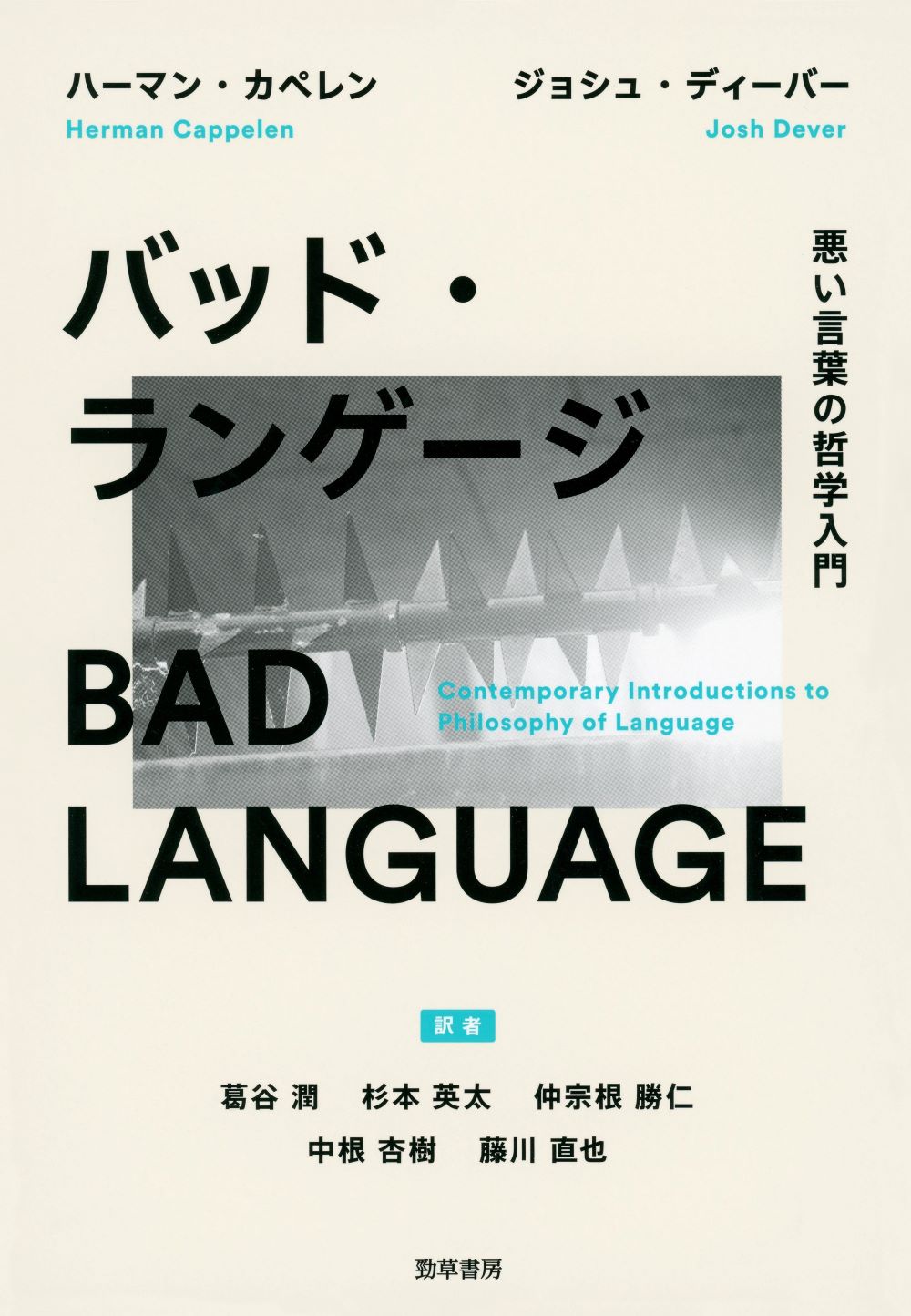
 eBook
eBook