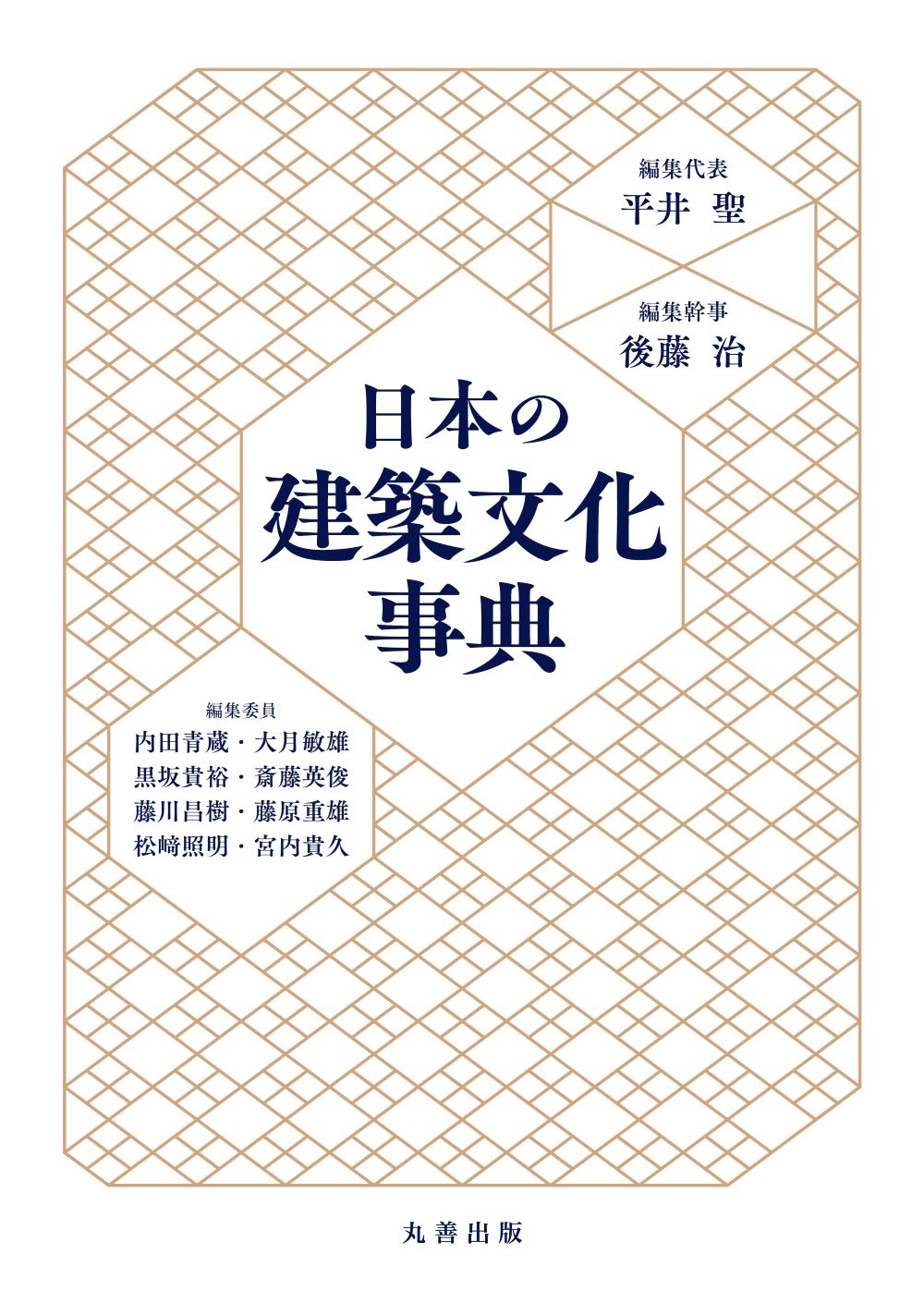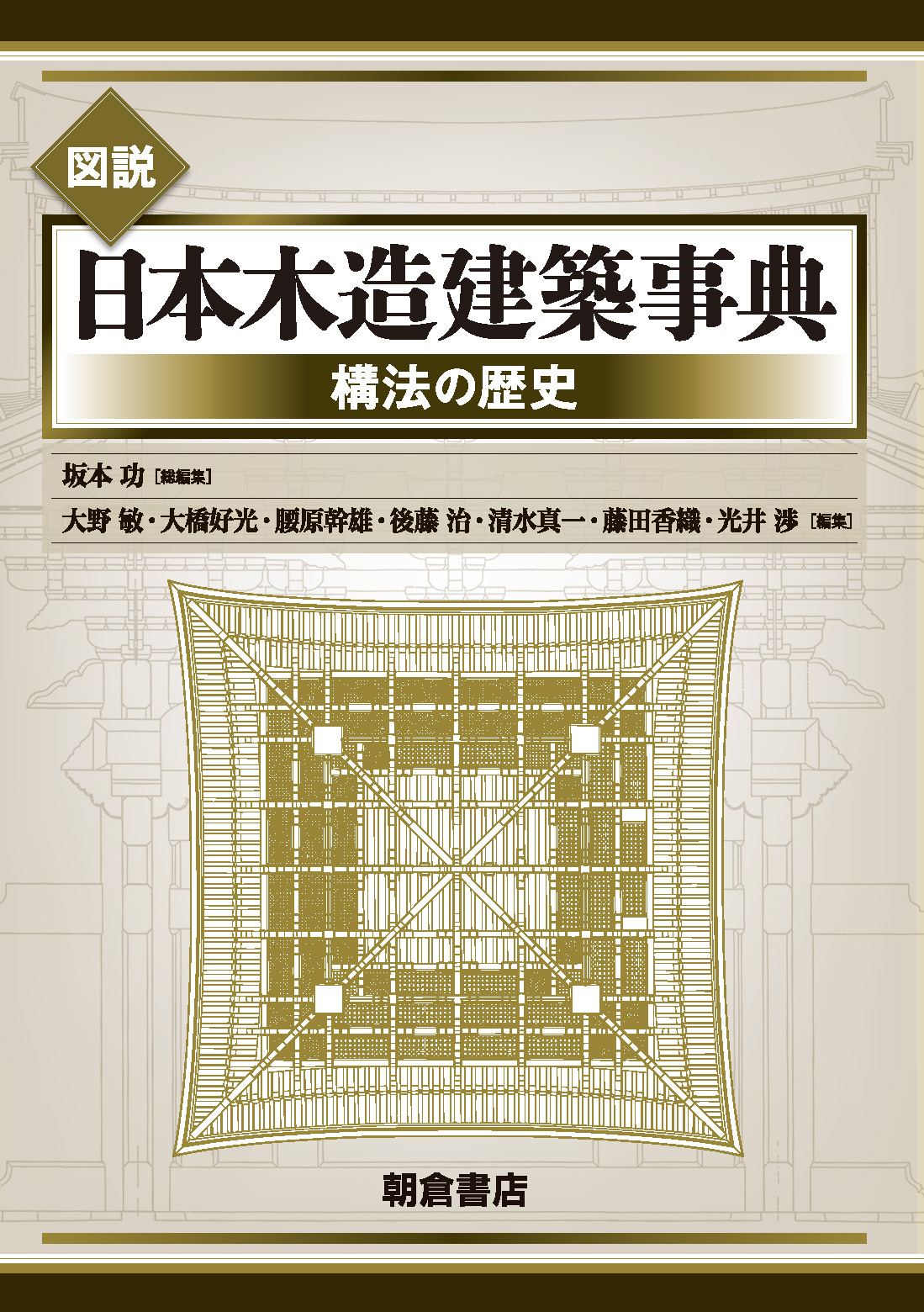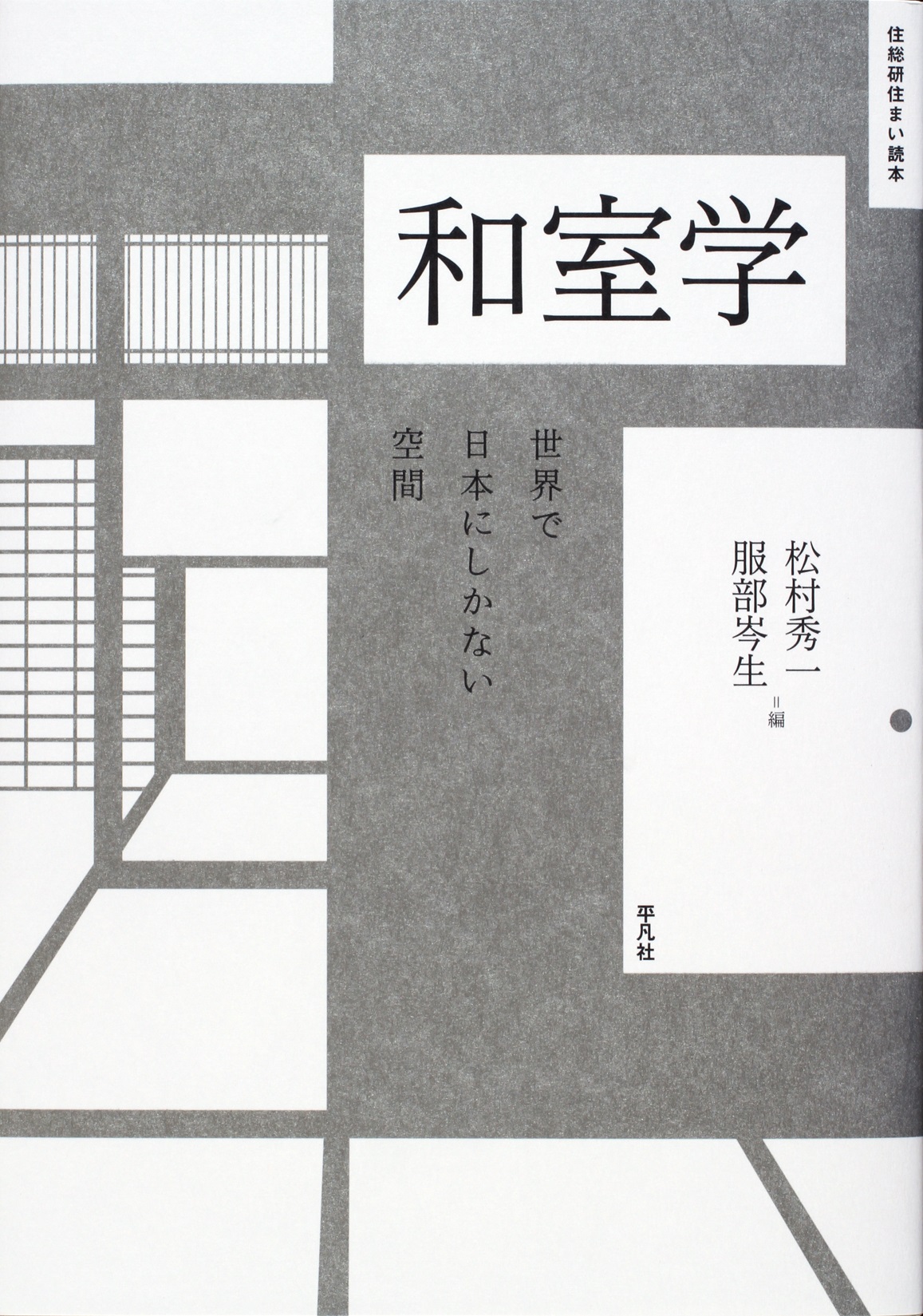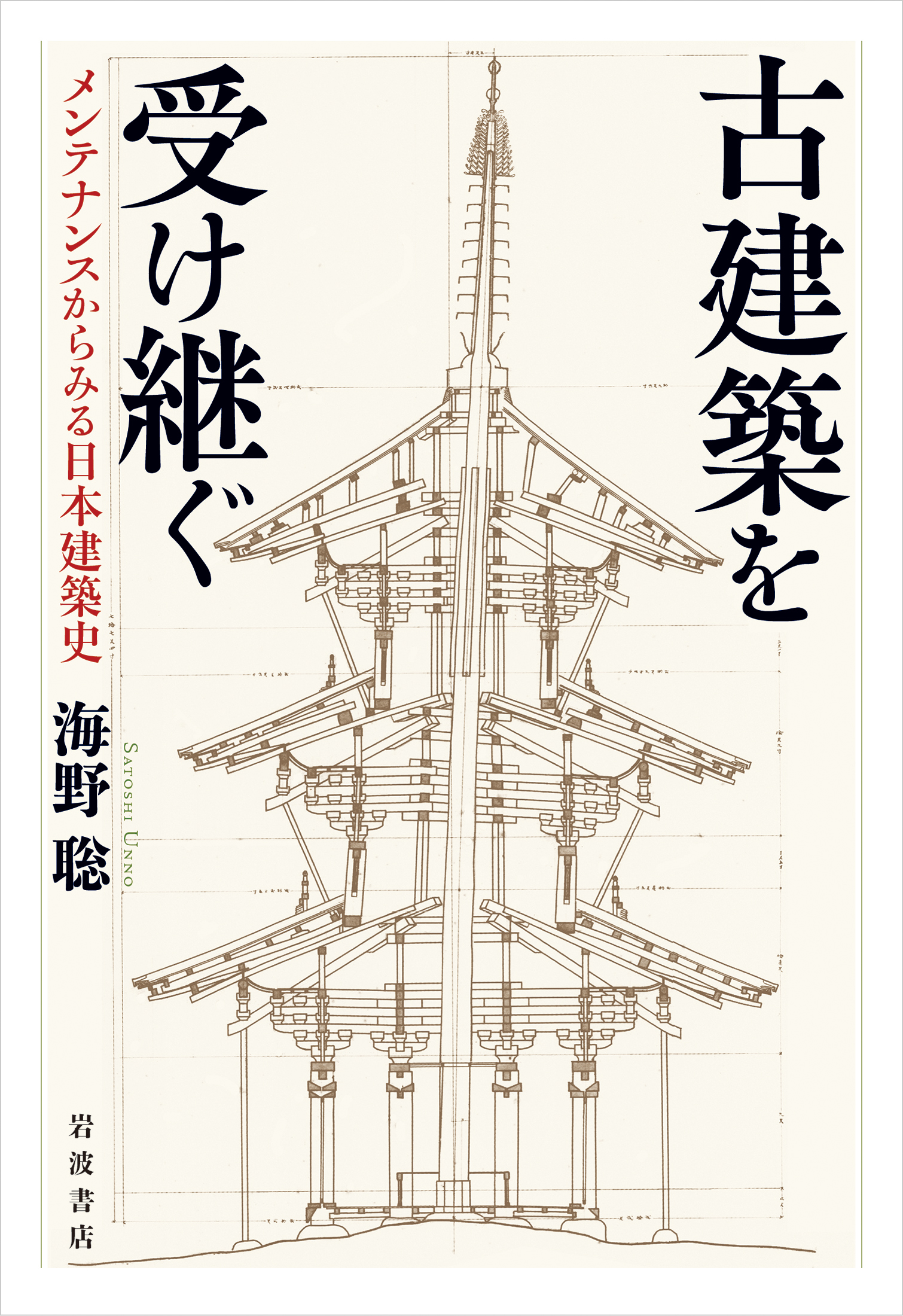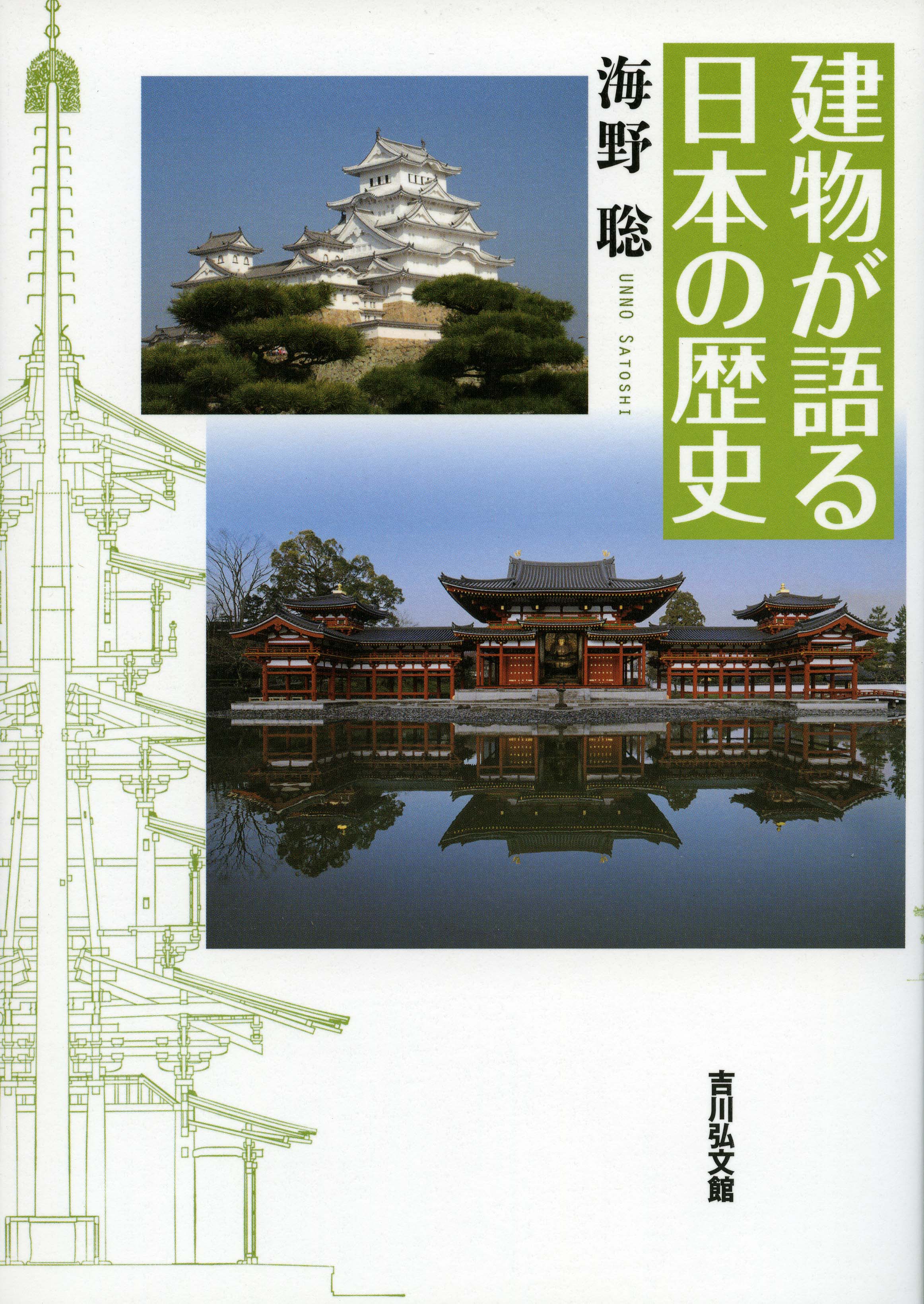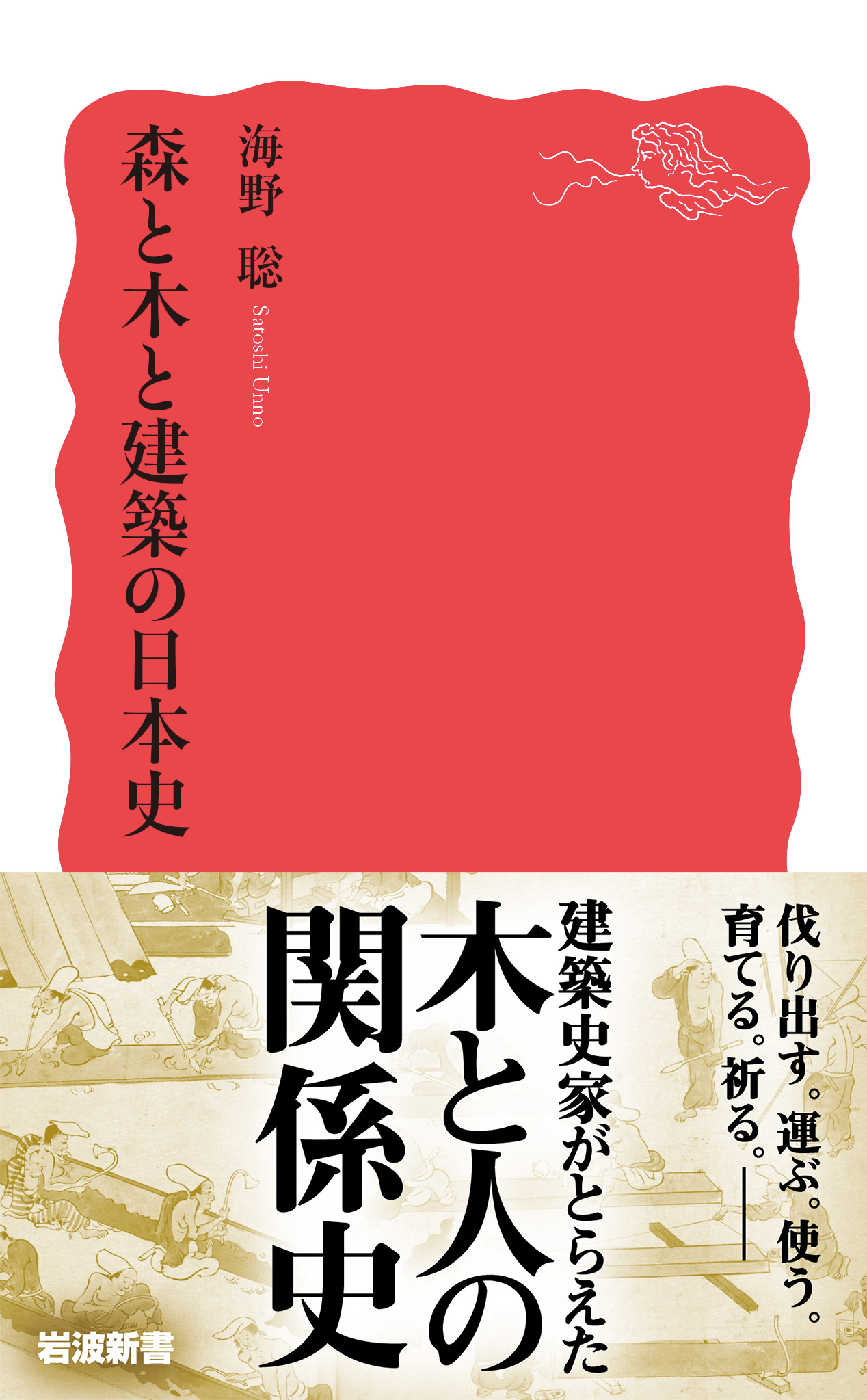本書は、「建築事典」ではなく「建築文化事典」であるというところに特色がある。日本独自の文化、それは言葉や振る舞い、文学や芸術、風景や景色、作法や制度、技や知恵、音色や味といった様々なものに埋め込まれているものであり、文化そのものを取り出そうとしても、なかなかできるものではない。我々の身の回りにある現象の中に、長い歴史の中で刷り込まれた文化的なものの香りをほのかに嗅いだり、味わったり、気になったりすることを通して、文化とは認識されるものであろう。こうした文化の中でも、「日本の建築」にまつわる文化的事象をとり上げ、それらがどのような歴史的経緯を経ながら、我々の眼前に存在しているのか、といったことを解説することを、本書は目指している。
例えば、我々が日常過ごしている住宅には通常、「玄関」という空間がある。これはもちろん靴を脱ぐための空間である。しかしよく考えてみると、世界中で、この靴を脱ぐことを主たる目的とした独立した空間を、固有名詞とともにもっているのは、日本人くらいなものである。そして、その歴史を紐解いてみると、この空間が、はるか昔の竪穴式住居の土間空間の生き残り、残影でもあると解釈できる。家の中がすべて地面であった頃の生活から、徐々に、住宅の中に床が貼られていき、現代に残った空間が玄関の土間なのである、というふうな解釈ができる。こんな事がわかったら、外国の友達に、生き生きと玄関を説明できるのではないだろうか。本書は、例えば、そんな「事」の事典なのである。
全10章331項目からなる本書は、かつてNHKの大河ドラマの時代考証もやっていた平井聖東京工業大学 (現・東京科学大学) 名誉教授を編集代表として、後藤治、元・工学院大学理事長を編集幹事とする、総勢10名の専門家で構成された委員会によって編集された。331項目の執筆者は157名を数える。この編集委員は、私を除いてみんな建築史の専門家で、私一人だけが建築計画学という異分野の学者だった。建築文化を紐解くのが本書の主たる業務なので、当然歴史の専門家が主体なのであるが、「各種施設」という近現代特有の建築物に関わる事柄は歴史の専門家の手には負えない。学校建築、病院建築、図書館建築、工場、美術館、こうした近現代をかたちづくる専門的建築の成り立ちを研究している建築計画学の観点から、これらがどのように近代に生じて、現代の文化とどのようにつながっているかを記述するために、私が加わり、「第7章:近現代のかたち」が編まれている。
古代から現代に至るまでの、建築に関わるあらゆる文化的現象の成り立ちを紐解くことを目指した本書は、空間にまつわる数多くの疑問に答えようと作られたのだが、もし、本書で解説されていないような事柄があれば、それは、十分に研究論文のネタになる事柄であるとも言ってよいだろう。
(紹介文執筆者: 工学系研究科 教授 大月 敏雄 / 2025)
本の目次
第2章:伝統的なつくり(担当編集委員:斎藤英俊)
第3章:伝統的なかたち(担当編集委員:黒坂貴裕)
第4章:寺社仏閣 祈りのかたち(担当編集委員:松崎照明)
第5章:伝統的な建築とくらし(担当編集委員:宮内貴久、内田青蔵)
第6章:近現代のつくり(担当編集委員:後藤 治)
第7章:近現代のかたち(担当編集委員:大月敏雄)
第8章:近現代の建築とくらし(担当編集委員:内田青蔵、宮内貴久)
第9章:都市とのかかわり(担当編集委員:藤川昌樹)
第10章:建築小話(担当編集委員:藤原重雄)



 書籍検索
書籍検索