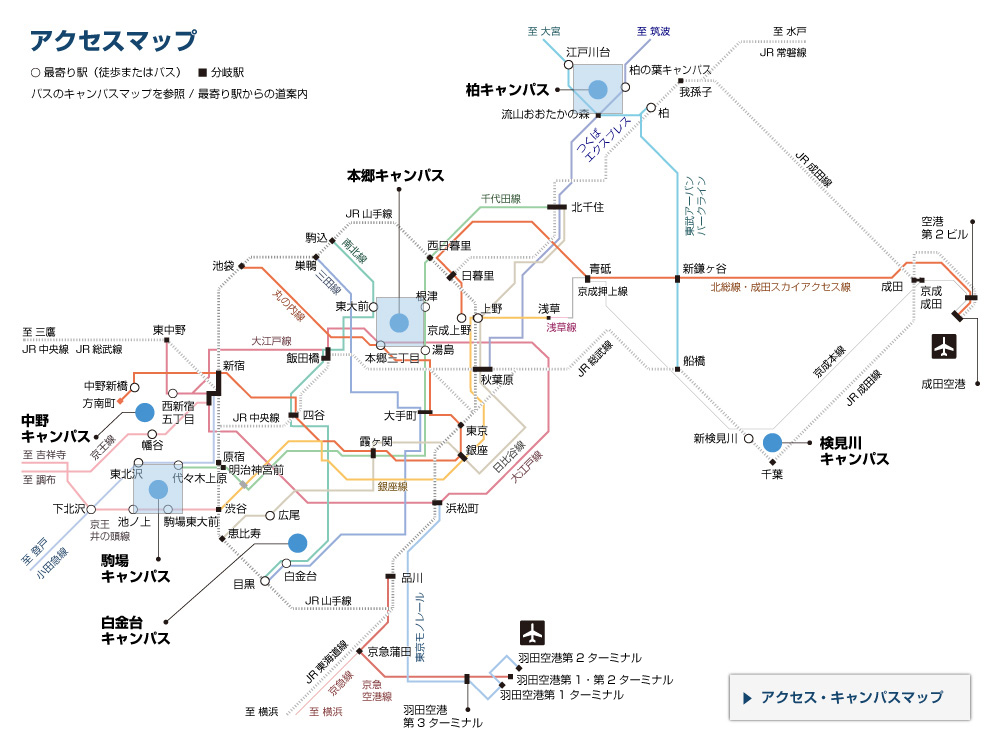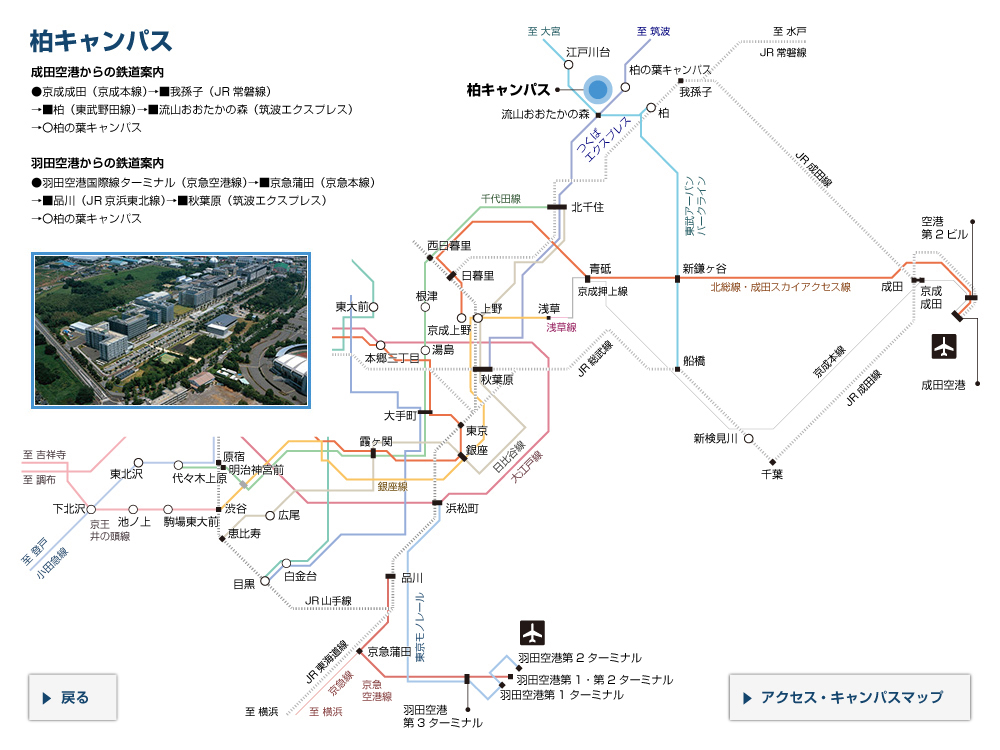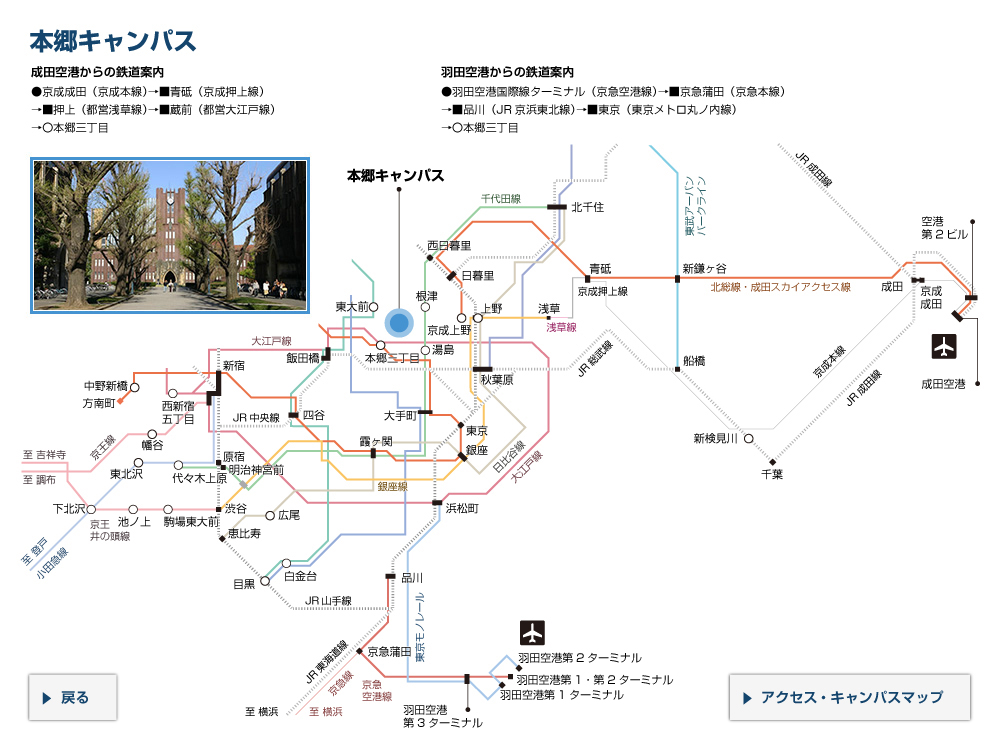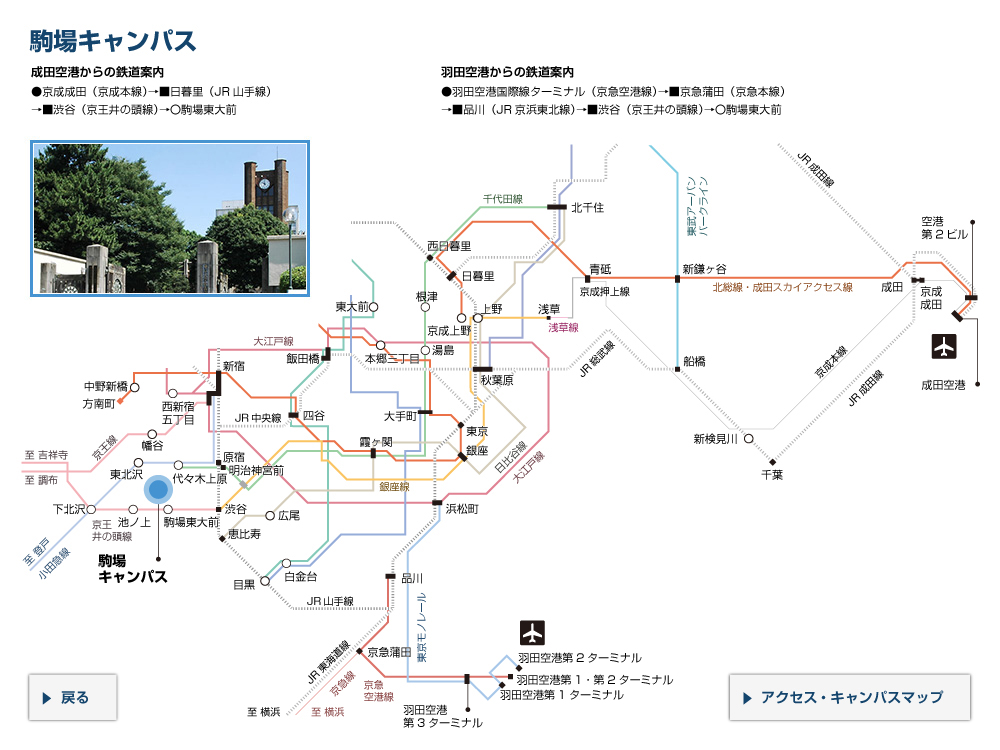東京大学稷門賞
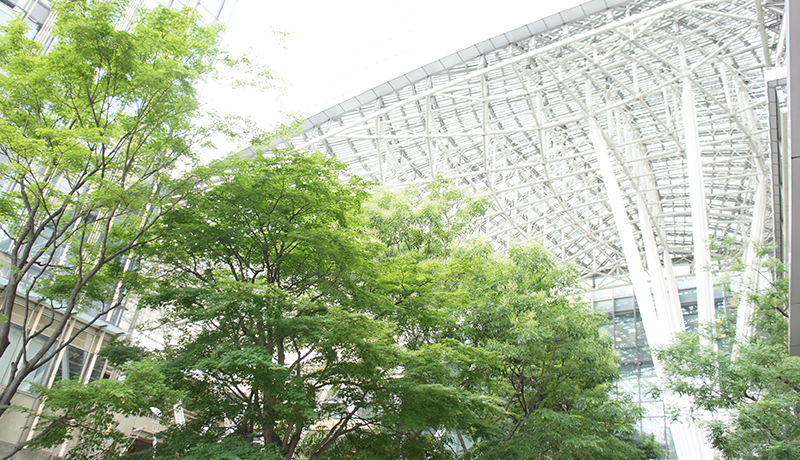
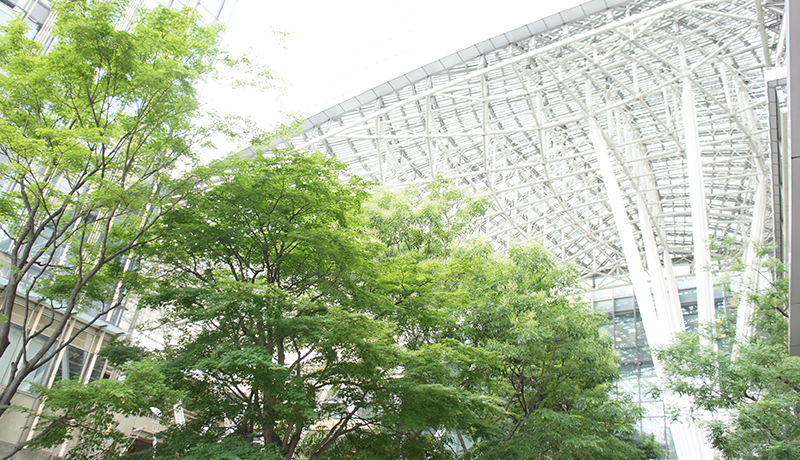
東京大学稷門(しょくもん)賞
本学は、平成14年度から本学に私財の寄附、ボランティア活動及び援助、寄付講座、寄付研究部門等により、本学の活動の発展に大きく貢献した個人、法人又は団体に対し、感謝の意を表すため「東京大学功績者顕彰制度」を設け、その功績に対し「東京大学稷門賞」を贈呈しています。(現に在籍する本学の教職員及び学生を除きます。) なお「稷門」とは、中国の戦国時代の斉(現在の山東省)の首都の城門の名前です。斉の威王、宣王が学者を厚遇したので、斉の都に天下の賢者が集まり、学問が栄えたという故事をこの賞の名称は踏まえています。稷門付近は「稷下」と呼ばれ、多くの学者が集まったことから、「稷下の士」という言葉も生まれました。(出典『史記』)
東京大学稷門賞受賞者(過年度の受賞者はこちらからご覧になれます。東京大学稷門賞受賞者一覧 (PDFファイル: 578KB) )
| 授賞年度 | 受賞者 | 授賞理由 |
|---|---|---|
| 令和7(2025)年度 | 末永 直行 様、末永 博子 様 | 同氏は、会社経営の傍ら福岡の文化・教育・経済各界で幅広く活動した音楽評論家で、特に日仏交流に力を注いだ。その過程で所有した出色の名器、プレイエル社(フランス)1952年製モデルALコンサートグランドピアノを寄贈いただいた。ピアノの修復及び演奏会開催の費用も併せてご寄附いただき、大規模な修復を経て2024年3月に先端科学技術研究センターENEOSホールで記念コンサートが開催された。この歴史的なピアノを基点に、芸術が繋ぐ異分野間の研究者や社会のステークホルダーとの「響創」がキャンパスにおいて日常的に展開されることが期待される。歴史的・文化的に大変貴重なピアノの寄贈により、本学における芸術環境創造の進展に寄与された点が評価された。 |
| 東京大学法科大学院同窓会 様 | 同同窓会は、[1]法科大学院関係者の人的ネットワークの構築に寄与するとともに、[2]法科大学院学生に対する「未修者指導」を運営して法学未修者に対する法律文書作成指導や学修上の助言を行い、その教育の一翼を担い、また、学生・修了生等の進路選択について貴重な情報提供を行うなど、継続的に学生に対するサポート事業を行っている。さらに、[3]最近では法科大学院20周年記念の寄附事業において、多額のご寄附をいただくなど、法科大学院の教育に対する経済的な支援を継続的にいただいている。これらの多面的な貢献は、法科大学院の教育に対して極めて重要な価値を有するとともに、同窓会組織が学生の教育支援を担い、財政的な支援の中核として機能している点は、今後の大学における支援のあり方を示す好例としても評価された。 | |
| オマーン・スルタン国政府 様 | 本学初の永久寄付講座としてスルタン・カブース・グローバル中東研究寄付講座を教養学部・大学院総合文化研究科に2011年に創設して以来、教育・研究・社会貢献の分野に多大なご支援を頂いている。寄付講座を中核として設立された中東地域研究センター(UTCMES)は、本学における中東研究の拠点として発展し、オマーン・スルタン国を始めとする中東諸国との交流拠点として機能している。ニューズレターを含む多数の刊行物が出版されているほか、本学所属の若手研究者を含む国内外の研究者が登壇する公開セミナーが定期的に開催されるなど、本学における教育、研究、国際交流の発展に多大な貢献があったことが評価された。 | |
| みずほ証券株式会社 様 | みずほ証券寄付講座「資本市場と公共政策」は2007年4月に設置され、資本市場およびファイナンスに関する講義を開講するとともに、公共政策の観点から資本市場の在り方や適切な規制・監督の在り方について研究を行っている。特に、業界の実態を踏まえた適切な規制を考えるうえで、中立的な立場に立つ大学が、民間企業と規制官庁との対話の場を提供し、そこに学術的知見を提供することの重要性は高く、同寄付講座はその中心的役割を担っている。その研究成果はシンポジウムやセミナーを通じて積極的に社会に発信され、公開の場での幅広い議論を促進することに寄与している。このように、同寄付講座は、公共政策大学院における教育研究基盤の形成と人材育成に対し、長年にわたり多大な貢献を果たしているのみならず、社会的課題の解決に資する学術研究とその社会発信を行っている点が高く評価された。 |