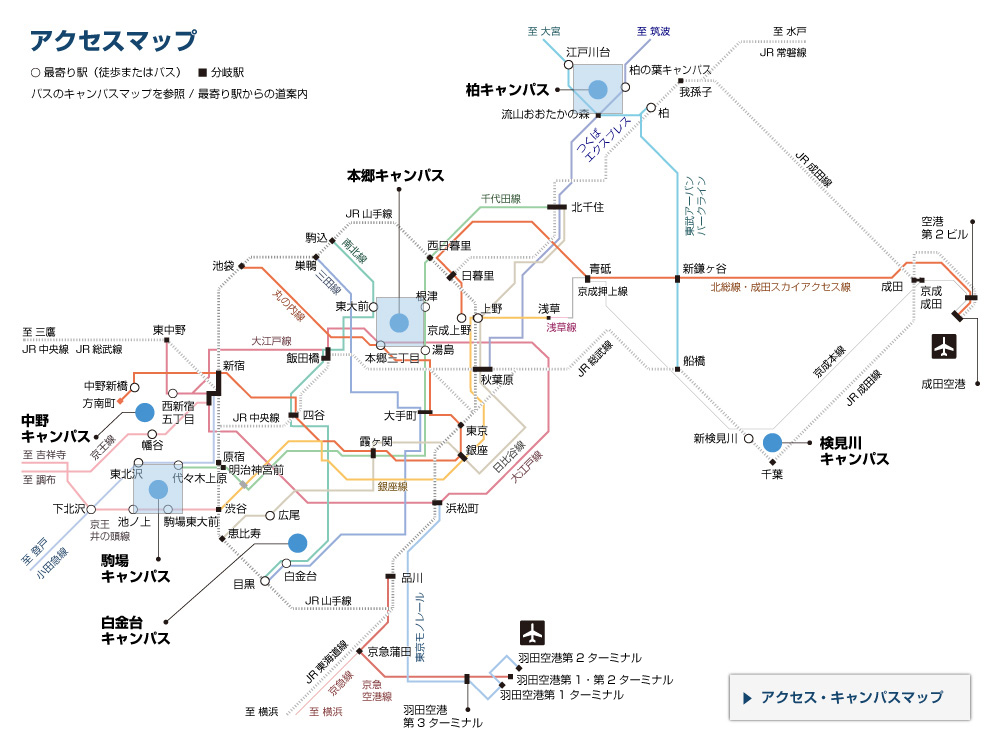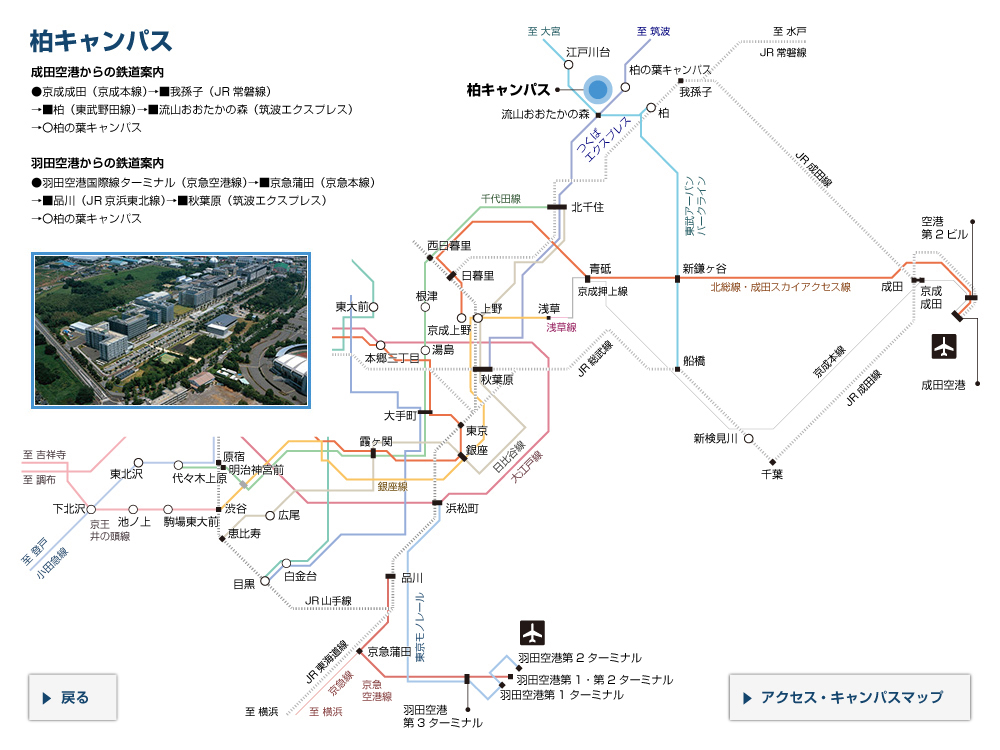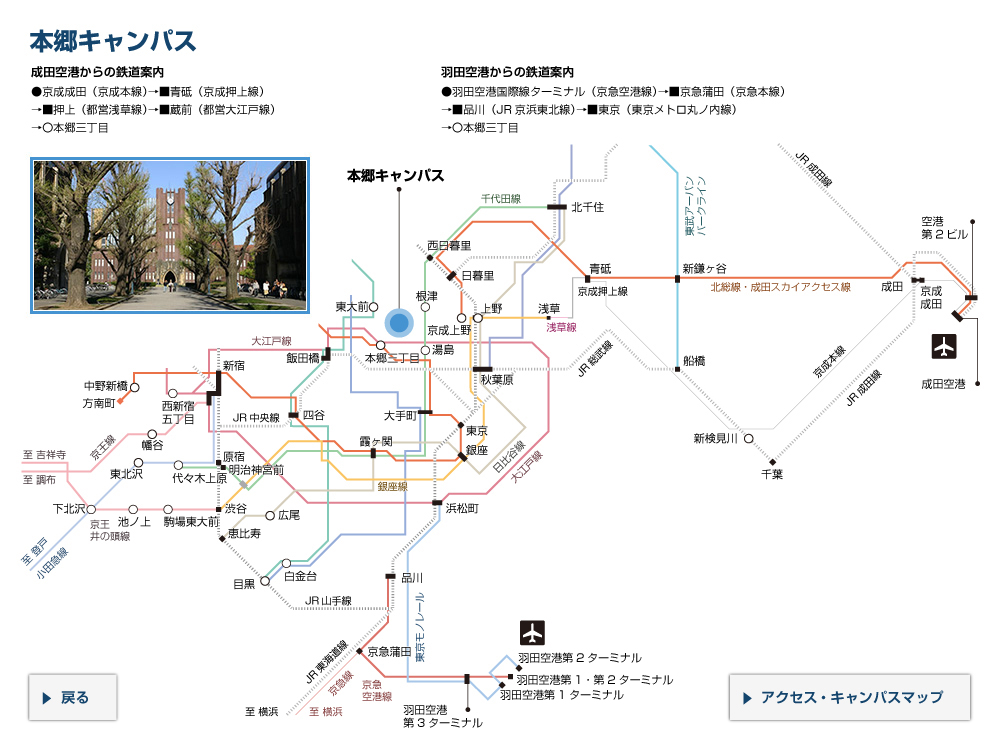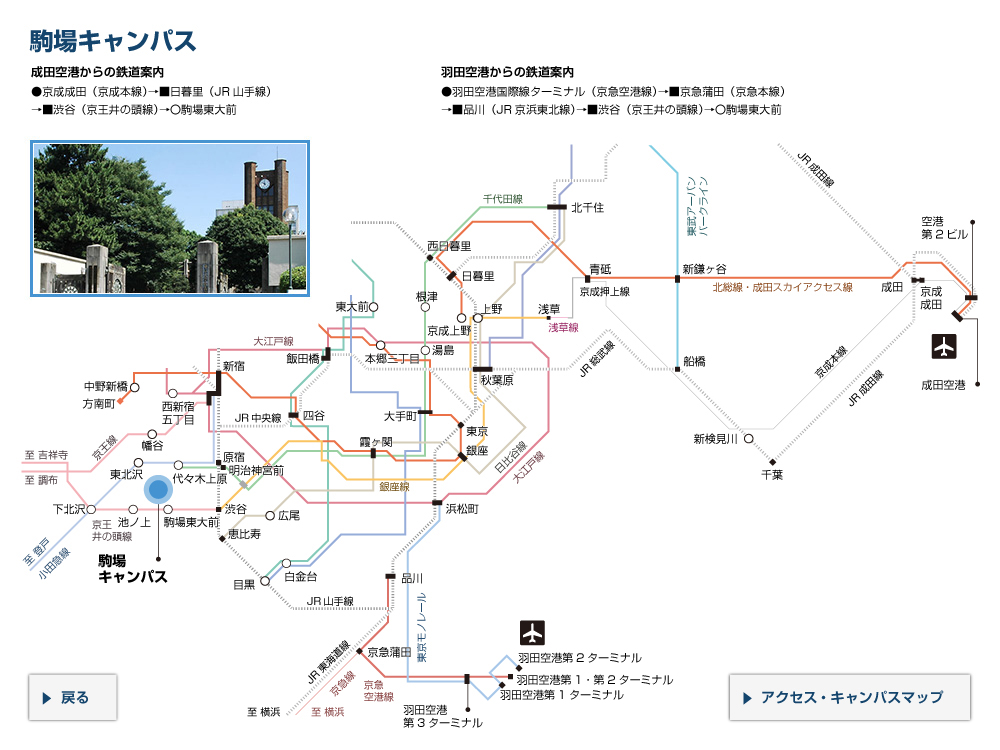【東京大学基金】調査から連携へ 東京大学と釜石市のふるさと納税連携が拓く新たな地域創生の形
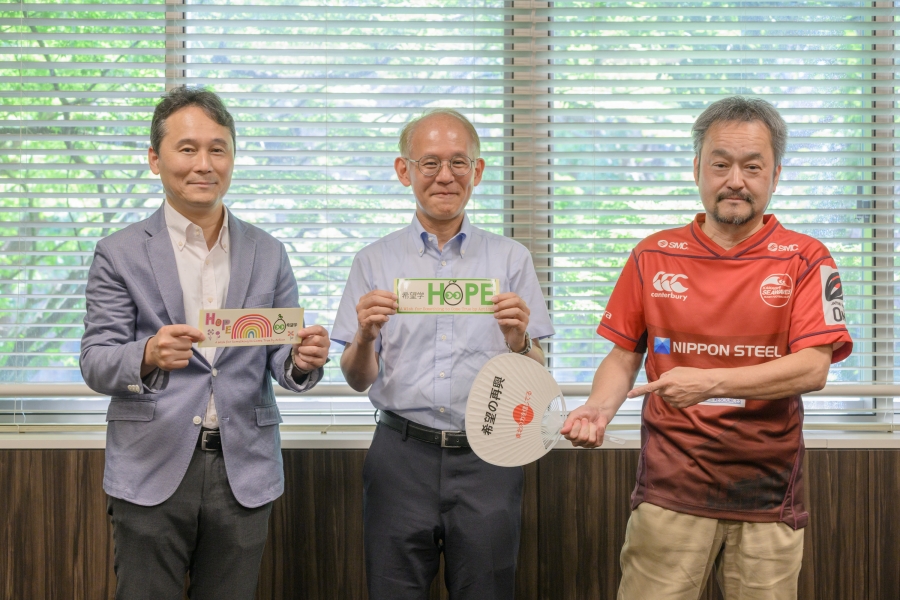
東京大学と釜石市のふるさと納税連携が拓く、新たな地域創生の形
東京大学と岩手県釜石市が9月に締結したふるさと納税連携協定は、20年におよぶ「希望学」プロジェクトから育まれた深い絆が結実したものです。本協定では、地域に眠る「珠玉の名言」を、新たな物語として紡ぎ直すことで、持続可能な地域創生を目指します。この画期的な連携により、単なる返礼品競争ではない、知恵と物語を軸としたふるさと納税の新たな可能性が拓かれます。これまでの挑戦の軌跡と未来展望をお届けします。
宇野所長: 社会科学研究所(以下「社研」)は釜石とは本当に長いお付き合いです。「希望学」を始めた2006年に釜石を訪れて以来、ずっと関係を続けてきました。そして2018年には大気海洋研究所(以下「大海研」)と社研で「海と希望の学校in三陸」を始め、2022年には大海研と先端科学技術研究センターと社研が組んで「海と希望の学園祭in釜石」を立ち上げ、そこに生産技術研究所も加わりました。現在、文理を超えて四研究所が合同で、東京大学の研究所と釜石の交流が続いています。
玄田教授: きっかけは津田敦さん*なんですよ。大海研が大槌にありながら、地域に馴染めていないという危機感があったんです。そこで「何かできないか」と相談されて、「じゃあ、まずタイトルを決めよう」と。大海研は海、私たちは希望ということで「海と希望の学校in釜石」が生まれました。その後、「海と希望の遠足」や「海と希望の学園祭」もやり、だんだん広がって今に至ります。 楽しみながらやっているんですよ。きっかけよりも続けることが大事です。
*津田敦。東京大学理事。地域連携担当。大海研・所長を経て、現職。
玄田教授: お互い、文系・理系って気にしてないと思うんですよね。一度みんなでプレゼンをやってもらったんです。温泉に泊まり込んで合宿で、「自分の研究はこんな研究です」というのを。とても楽しくやっているところというのがあります。 すごい研究者って、ちょっと余裕があったり、いろんなことに関心があったりします。自分の研究だけしていていいのか、自分たちの研究を支えている地域の人とか、その地域に生きる子どもたちのことを考えなくていいのか、みたいな真剣な思いを聞くと、「それを大切にしなきゃいけないな」と思いました。そういう意味では、すごく幸せな出会いでしたね。
宇野所長: やっぱり楽しいですね。大海研の人たちは最初、「社研は一般の市民に向けて話すのに慣れているだろう」と言っていたんです。でも例えば、峰岸有紀さん*は鮭の研究に情熱を注ぎ、福田秀樹さん*は海上浮遊物の専門家で、海の上に浮かぶものを見つけると目を輝かせる。彼らの熱意は本当に素晴らしいんです。
中村教授: むしろ我々の方が、「大海研にこんなタレントの人が揃っているんだ」と思って、面白くなってきました。彼らが社研の魅力を引き出してくれたと思います。大海研が社研に関心を持ってくれたのは、市役所との関係だと思います。社研は20年近く活動していて、それに驚いたんじゃないでしょうか。
玄田教授: すごくラッキーだったんですよ。釜石は製鉄所があった関係で人の出入りが多く、他所者に対して非常にオープンなんです。東日本大震災を経て、さらに次の調査が始まり、長く付き合ううちに信用してもらいました。
宇野所長: 釜石は本当に勉強好きな人が多いんです。「一般市民相手だから話を分かりやすくしよう」みたいなことを言うと、「そうじゃない、私はちゃんと調べました」と怒られることもあります。郷土史家の方もいらっしゃったり、日本の地域には本当にインテリが多いと感じました。
玄田教授: 地域にお邪魔するときの姿勢も重要です。私たちは「仮説を検証するために地域に行くな」という姿勢で、その地域に入って、そこで考えることを大事にしました。希望を持ってやっている人は、だいたい過去につらい経験や深刻な試練を経験してきた人たちで、それでも前を向くときに「希望」というものに思いを託すんです。
宇野所長: 最初は警戒されましたよ。「何しに来たんだ」って。「調査公害」なんて言われた時期ですから、研究者がワーッと来て調査して、サッと帰って、論文を書いておしまい。「お前らもそういう感じか」という疑いはずっとありました。その壁を突破できたからこそ、今でも信頼関係が続いています。
*峰岸有紀。大海研・准教授。
*福田秀樹。大海研・准教授。

中村教授: 釜石は1986年に最後の高炉の火が消え、「製鉄の街」とは言っていても80年代にすでに製鉄は終わっていました。80年代から街をどうにかしなければと議論し、いろんなことをやってきた中で東日本大震災が来ました。釜石はある意味で、日本の津々浦々で今経験しているようなことを30年以上前から繰り返し経験していて、しかしその中からどうやって希望を見出すかというと、楽しい未来があるから頑張るというよりも、しんどくて大変だからこそ、前を向いていくたびに希望が出てくるわけです。 「地域における希望の再生にとって必要な要素は何だろう」という問題意識をもって釜石市の地域調査を行い、結果として「ローカルアイデンティティの再構築」「地域内外のネットワーク形成」「希望の共有」という3つの要素に注目しました。釜石のローカルアイデンティティの再構築は今も続いていて、「鉄と魚とラグビーの街」を掲げていますが、実はどれも衰退していて難しい面があります。地域内外のネットワークは震災の前後に新たな段階に入り、非常に広がっています。希望の共有は、みんながどういう地域としての目標を持っているかということですが、これについてもバラバラなところがあります。
玄田教授: 2010年に東大出版会から希望学の本を4巻出しました。NHKの「クローズアップ現代」で取り上げられたりして、釜石市で取材し、「希望の街」みたいな感じになったときもありました。私たちが釜石で学んだことは、希望というのはどんなに苦しくても、一人一人が自分たちの手で作っていくものだということ。誰かに希望を与えようなどという傲慢なことは考えてはいけない。一人一人が自分たちで希望を育んでいくことが尊いことであって、それをみんなで支え合うことが大事だということが、私の中では最大の発見でした。
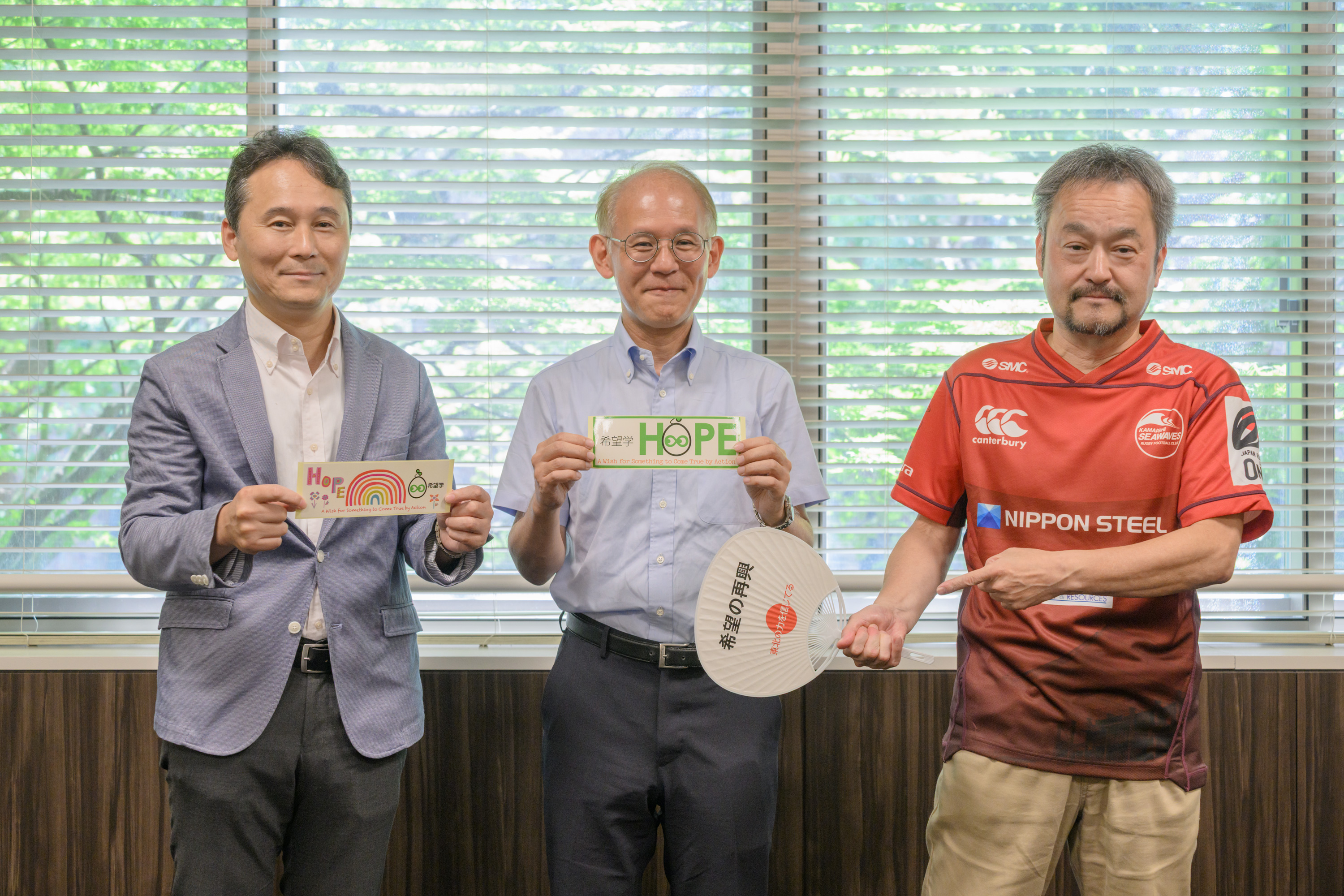 宇野 重規(うの・しげき)
宇野 重規(うの・しげき)
社会科学研究所・所長。専門は、政治思想史・政治哲学。東京大学法学部卒業、博士(法学)。
千葉大学を経て、現在、社会科学研究所教授。主な著書に、『トクヴィル――平等と不平等の理論家』『〈私〉時代のデモクラシー』『民主主義のつくり方』、『政治哲学的考察――リベラルとソーシャルの間』『保守主義とは何か』。
玄田 有史(げんだ・ゆうじ)
執行役・副学長。専門は、労働経済学。東京大学経済学部卒業。経済学博士。ハーバード大学、オックスフォード大学各客員研究員、学習院大学教授等を経て、現在、社会科学研究所教授。主な著書に『仕事のなかの曖昧な不安』『希望のつくり方』。
中村 尚史(なかむら・なおふみ)
社会科学研究所教授。専門は、日本経済史・経営史。熊本大学卒業。九州大学大学院修了、博士(文学)。埼玉大学助教授、シェフィールド大学、LSE、EHESS, ハーバード大学の客員教授、客員研究員等を経て、現在同職。主な著書に『日本鉄道業の形成』、『地方からの産業革命』、『海をわたる機関車』。
釜石市ふるさと納税
地域連携で大学が貢献できること―釜石市との20年から見えてきたもの
本日は「地域連携で大学が貢献できることとは何か」というテーマで、東京大学と釜石市との20年にわたる連携から見えてきたことについて、お三方にお話を伺います。最初に「海と希望の学園祭in釜石プロジェクト」について、その経緯を教えていただけますか。宇野所長: 社会科学研究所(以下「社研」)は釜石とは本当に長いお付き合いです。「希望学」を始めた2006年に釜石を訪れて以来、ずっと関係を続けてきました。そして2018年には大気海洋研究所(以下「大海研」)と社研で「海と希望の学校in三陸」を始め、2022年には大海研と先端科学技術研究センターと社研が組んで「海と希望の学園祭in釜石」を立ち上げ、そこに生産技術研究所も加わりました。現在、文理を超えて四研究所が合同で、東京大学の研究所と釜石の交流が続いています。
玄田教授: きっかけは津田敦さん*なんですよ。大海研が大槌にありながら、地域に馴染めていないという危機感があったんです。そこで「何かできないか」と相談されて、「じゃあ、まずタイトルを決めよう」と。大海研は海、私たちは希望ということで「海と希望の学校in釜石」が生まれました。その後、「海と希望の遠足」や「海と希望の学園祭」もやり、だんだん広がって今に至ります。 楽しみながらやっているんですよ。きっかけよりも続けることが大事です。
*津田敦。東京大学理事。地域連携担当。大海研・所長を経て、現職。
他の研究所との取り組みがもたらした相乗効果
大海研との連携について、何か相乗効果はありましたか?玄田教授: お互い、文系・理系って気にしてないと思うんですよね。一度みんなでプレゼンをやってもらったんです。温泉に泊まり込んで合宿で、「自分の研究はこんな研究です」というのを。とても楽しくやっているところというのがあります。 すごい研究者って、ちょっと余裕があったり、いろんなことに関心があったりします。自分の研究だけしていていいのか、自分たちの研究を支えている地域の人とか、その地域に生きる子どもたちのことを考えなくていいのか、みたいな真剣な思いを聞くと、「それを大切にしなきゃいけないな」と思いました。そういう意味では、すごく幸せな出会いでしたね。
宇野所長: やっぱり楽しいですね。大海研の人たちは最初、「社研は一般の市民に向けて話すのに慣れているだろう」と言っていたんです。でも例えば、峰岸有紀さん*は鮭の研究に情熱を注ぎ、福田秀樹さん*は海上浮遊物の専門家で、海の上に浮かぶものを見つけると目を輝かせる。彼らの熱意は本当に素晴らしいんです。
中村教授: むしろ我々の方が、「大海研にこんなタレントの人が揃っているんだ」と思って、面白くなってきました。彼らが社研の魅力を引き出してくれたと思います。大海研が社研に関心を持ってくれたのは、市役所との関係だと思います。社研は20年近く活動していて、それに驚いたんじゃないでしょうか。
玄田教授: すごくラッキーだったんですよ。釜石は製鉄所があった関係で人の出入りが多く、他所者に対して非常にオープンなんです。東日本大震災を経て、さらに次の調査が始まり、長く付き合ううちに信用してもらいました。
宇野所長: 釜石は本当に勉強好きな人が多いんです。「一般市民相手だから話を分かりやすくしよう」みたいなことを言うと、「そうじゃない、私はちゃんと調べました」と怒られることもあります。郷土史家の方もいらっしゃったり、日本の地域には本当にインテリが多いと感じました。
玄田教授: 地域にお邪魔するときの姿勢も重要です。私たちは「仮説を検証するために地域に行くな」という姿勢で、その地域に入って、そこで考えることを大事にしました。希望を持ってやっている人は、だいたい過去につらい経験や深刻な試練を経験してきた人たちで、それでも前を向くときに「希望」というものに思いを託すんです。
宇野所長: 最初は警戒されましたよ。「何しに来たんだ」って。「調査公害」なんて言われた時期ですから、研究者がワーッと来て調査して、サッと帰って、論文を書いておしまい。「お前らもそういう感じか」という疑いはずっとありました。その壁を突破できたからこそ、今でも信頼関係が続いています。
*峰岸有紀。大海研・准教授。
*福田秀樹。大海研・准教授。

希望学の視点から見た釜石市の20年
希望学の視点から見た釜石市の20年は、どのような特徴がありますか?中村教授: 釜石は1986年に最後の高炉の火が消え、「製鉄の街」とは言っていても80年代にすでに製鉄は終わっていました。80年代から街をどうにかしなければと議論し、いろんなことをやってきた中で東日本大震災が来ました。釜石はある意味で、日本の津々浦々で今経験しているようなことを30年以上前から繰り返し経験していて、しかしその中からどうやって希望を見出すかというと、楽しい未来があるから頑張るというよりも、しんどくて大変だからこそ、前を向いていくたびに希望が出てくるわけです。 「地域における希望の再生にとって必要な要素は何だろう」という問題意識をもって釜石市の地域調査を行い、結果として「ローカルアイデンティティの再構築」「地域内外のネットワーク形成」「希望の共有」という3つの要素に注目しました。釜石のローカルアイデンティティの再構築は今も続いていて、「鉄と魚とラグビーの街」を掲げていますが、実はどれも衰退していて難しい面があります。地域内外のネットワークは震災の前後に新たな段階に入り、非常に広がっています。希望の共有は、みんながどういう地域としての目標を持っているかということですが、これについてもバラバラなところがあります。
玄田教授: 2010年に東大出版会から希望学の本を4巻出しました。NHKの「クローズアップ現代」で取り上げられたりして、釜石市で取材し、「希望の街」みたいな感じになったときもありました。私たちが釜石で学んだことは、希望というのはどんなに苦しくても、一人一人が自分たちの手で作っていくものだということ。誰かに希望を与えようなどという傲慢なことは考えてはいけない。一人一人が自分たちで希望を育んでいくことが尊いことであって、それをみんなで支え合うことが大事だということが、私の中では最大の発見でした。

釜石市全景

橋野鉄鉱山は現存する国内最古の高炉跡として知られる

橋野鉄鉱山は現存する国内最古の高炉跡として知られる
釜石の地域的な強みと可能性
釜石の地域的な強みや可能性について、どのようにお考えですか?玄田教授: 釜石は「鉄と魚とラグビーの街」と言われていますが、現実は変わってきています。でも衰退するかというと、そんなことはなくて、KNT理論なんですよ(笑)。釜石には小ネタ(KNT)がたくさんあるんです。小ネタ理論と呼んでいますが、人口が減ったからといって街がすぐなくなるわけではない。むしろ小ネタが尽きたときに街が厳しくなる。逆に小ネタが豊富である地域は、そう簡単にはダメにならない。 ふるさとを応援すべきことは大ネタだけではない。大切なのは、市民の持っている小ネタです。小ネタだから、ダメになることもあるけれど、そこから育んで大化けするかもしれない。小ネタをみんなで育てていくための栄養として、例えば、ふるさと納税にはものすごい期待をしています。 小さな希望の種を撒き続けることが大事で、それをどう応援できるかを考える必要があります。地域活性化といって一発大逆転を考えがちですが、そういう幻想から卒業しないと幸せになれません。もともとあった大きな物語は歴史として大事にしつつも、小ネタを大切に育てる街になってきているところに、一番希望を感じています。
宇野所長: 人口減少が続き、みんな関係人口、交流人口と言いますが、それだけでは元気は出てきません。やはりハッとする、心つかまれるような小ネタがいくらあるかで、その地域の未来は決まってくると思います。
玄田教授: 地域にある知恵と物語を、今の時世にあった形に転換をしていく。ナレッジ(Knowledge)、ナラティブ(Narative)、トランスフォーメーション(Transformation)・セオリー(Theory)、「KNT理論」です(笑)

漁旗が賑やかな海の祭典「釜石まつり」
ふるさと納税連携における今後の期待
ふるさと納税連携における今後の期待について教えてください。宇野所長: ふるさと納税の制度創設の背景には、地域で育てた子どもたちが都会に出て活躍し、税金も都会に納めるというアンバランスへの問題意識がありました。一人の人間は複数の場所と繋がりを持っているのに、税の仕組みは今の居住地に縛られています。 ふるさと納税は、いろんな地域に対する思いを納税・寄付という形で表現できる制度です。返礼品競争ではなく、具体的な事業を応援するという本来の筋に戻るべきだと思います。大学がここで貢献できるのは、地域の魅力ある小ネタや物語を見つけてくることです。いろんな地域に思いを持ち、つながりを持つ楽しさを伝えながら、この仕組みを活用していきたいです。
中村教授: 震災後、東京などで生活されている方から少額でも継続的な寄付をいただいています。釜石との関わりを続けるモチベーションになっていますし、活動の際の旅費などの実質的な支援にもなっています。一回の額は少額でも、積もると結構な額になるというのを実感として理解しており、ありがたく活用させていただいています。
玄田教授: ふるさと納税をする方には、それぞれ理由があるんじゃないでしょうか。税金対策ではなく、何か思いがあるからしてくださっているのだと思います。無関心や孤独ではなく、お互いが応援し合うというのは、この時代にとても大切なことだと感じています。
東京大学と釜石市の20年にわたる連携から見えてきたことについて、貴重なお話をいただきました。希望学から始まった調査で辿り着いた結論として、地域にある知恵と物語を今の時代に合った形で繋いでいくことの重要性が浮かび上がってきました。この長く深いつながりをさらに強固なものにするために、ふるさと納税連携を活用して、それぞれの新たな物語を増やしていきたいと思っています。
皆様からの温かい応援どうぞよろしくお願いいたします。
(担当:ディベロップメントオフィス・齋藤)
【ふるさと納税のしかた】
- インターネットで、各ふるさと納税ポータルサイトからお申し込み可能です。寄付の用途は、「釜石市と東京大学との連携事業の推進のため」を選択してください。寄付受付開始は、令和7年10月1日からとなります。 詳細は、釜石市ウェブサイトにて。
- もっと詳しく知りたい方は、東京大学社会科学研究所「釜石から社研が学んだこと」(動画) も合わせてご覧ください。
- 関連リンク:東京大学社会科学研究所 所長コラム